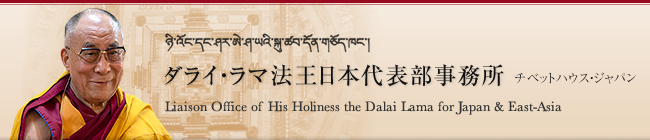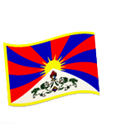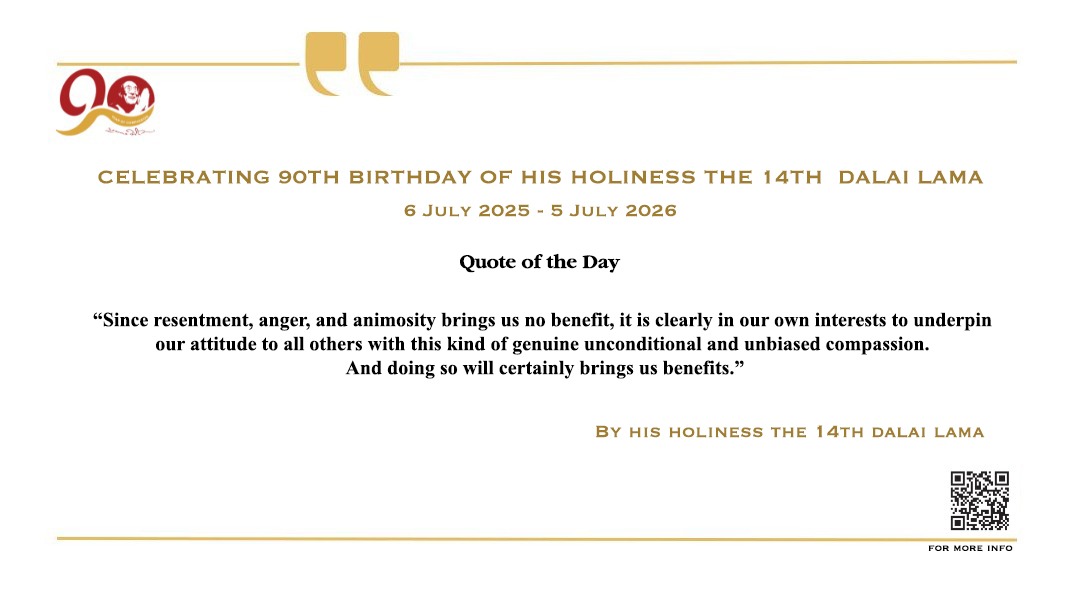翻訳:三浦順子
2001年10月6日(土)-7日(日) に 東京・太平会館で行われたニンマ派高僧トゥルシック・リンポチェによる説法会の内容をここに掲載いたします。
「37の菩薩の実践」とは
「37の菩薩の実践」は、13世紀の学者ギャルセー・トクメー・サンポが修行の階梯のかなめを37の詩のかたちで記したものです。著者の学識と修行経験に裏打ちされたこの「37の菩薩の実践」は、宗派を超えて愛され、修行の指針とされてきました。「37の菩薩の実践」の註釈は数多く存在しますが、今回の講義はトゥルシック・リンポチェの師ザトゥル・リンポチェ10世ガワン・テンジン・ノルブ(当事務所現代表の先代にあたる)の註釈をもとに、第四から第七の詩をとりあげ、詳しく解説いたします。扱うテーマは、今生への執着を捨てる、ラマへの帰依、三宝(仏・法・僧)への帰依といった仏教の礎となる教えです。
トゥルシック・リンポチェについて
トゥルシック・リンポチェは1924年、ラサに程近い大きい湖で知られるヤムドクのナンカツェで生まれました。4歳の時、ザトゥル・リンポチェ10世ガワン・テンジン・ノルブによって、トゥルシック・リンポチェ・ドンガ・リンパの転生者であると認定されました。
ザトゥル・リンポチェ十世から、重要なニンマ派の教え全てを伝授され、その後、ミンドリンのチュン・リンポチェとケン・リンポチェから教えを受けました。ミンドリンは、チベットのウ・ツァン地方にあるニンマ派最高峰の大学です。また、チベット仏教の他宗派の師のもとでも広範囲に亘って教えを受けました。
またトゥルシック・リンポチェは、ダライ・ラマ法王にニンマ派の教えを伝授した、現在最高位のラマの一人であり、ニンマ派の学者でもあります。
トゥルシック・リンポチェの僧院ツプテン・チョーリンは、ネパールの人里離れた場所にあり、700 人の僧と尼僧がいます。本国チベットでは僧院に入れる見込みも薄く、多くの若いチベット難民がトゥルシック・リンポチェから戎を授かりたいとツプテン・チョーリンにやってきています。
この説法会の開催経緯
数年前までトゥルシック・リンポチェは、世界中からの招待の申し出を断わってきましたが、ダライ・ラマ法王からのたっての要請があり、海外での教えの伝授を開始しました。しかし御高齢ということもあり、広範囲の旅行が不可能なので全ての人の希望を叶えることができません。それゆえ、東京での法話の招待を受けてくださったことは、大変幸運なことです。
チベット仏教に興味を持っていて、さらに学びたいと思っている皆様が、トゥルシック・リンポチェの法話に出席する機会を持てるようを心から願っております。
トゥルシック・リンポチェの健康状態を考慮し、セッションをとても短い時間に設定したことについて、ご参加の皆様のご理解を頂けるようお願い致します。各セッションが1時間30分より長くなることはありません。
トゥルシック・リンポチェ説法会における御寄付のお礼

トゥルシック・リンポチェの説法会にご参加の皆様から、五十万円にも昇るご寄付をいただき、私たちは非常に感激しております。
トゥプテン・チョーリン僧院は、チベット西部のトウ地域に在住の僧、尼僧が参詣することができる、唯一のチベット僧院です。トウ地域には仏教の説法会を行うことのできるラマ僧が一人もいないため、毎年、何百人もの見習僧がサブテン チョエリング僧院に集います。
トゥプテン・チョーリン僧院は、小規模の僧院で、四百人以上の僧、尼僧がすでに在籍しています。そのため、大勢の見習僧が押しかけた場合、僧院は、大変困難な状況に置かれることとなります。しかし、リンポチェは、すべての見習僧を受け入れ、衣食住を提供しております。見習僧たちは、チベットを脱出して以来、頼るべきものを失っているのです。
このような年若い僧、尼僧は、説法を拝聴し、勉学に勤しみ、人生を信仰の実践に捧げる決意でおります。そのため、皆さまからのご寄付は、見習僧たちの夢を実現するのに大きな助けとなることでしょう。トゥプテン・チョーリン僧院に寛大なご寄付をくださった、すべての慈悲深い方々に、心からの感謝を捧げたいと思います。
ダライ・ラマ法王日本代表部事務所代表
ザトゥル・リンポチェ
はじめに

まずこの場にわざわざ足を運んでくださった方々全員に、「タシデレ」(こんにちは)を申し上げます。日本は古い伝統文化を維持し、仏教徒の多い大国であると私は聞いています。仏教徒の多い国は人々の品性の高い国ともいえるのです。私がこの日本に来ることができたのも、ザトゥル・リンポチェがお招きくださったからです。ザトゥル・リンポチェの先代は私の根本のラマでもありました。
世界にはいろいろな宗教(dharma)があります。チベット人がなぜダルマを実践するのか(仏教の修行をするのか)というと、身体・言葉・心をよりよいものに変えていくためです。そして身体・言葉・心のなかでも一番肝心なのは心ですから、まず心を正さなくてはなりません。世界の宗教は、各々心を正していく技術をもっています。
仏教では、そのためにまず三宝、つまり仏陀・仏法・僧伽を知れと説いています。釈尊(仏陀)は12の偉業(兜率天からこの世におりてくる、悟りをひらく、大涅槃に入るなど)をなされ、そして仏法を、一切智に至る修行の道を説かれたのです。ですから我々は釈尊に対して考えも考えも及ばないほどの恩を負っているのです。
釈尊の説かれた正法は聖国インドにあまねく広まり、その後、雪の国チベットにも伝わりました。しかしこの世のすべては無常です。チベット本土で栄えていた仏教は今や見るかげもなく、ダライ・ラマ法王はインドに亡命されました。しかし亡命された結果、世界各国に赴かれ、チベット仏教を広めることになったのです。その後チベット仏教の各派――ニンマ・サキャ・カギュー・ゲルクの高僧たちが海外で布教をおこない、今や全世界でチベット仏教が広まっています。これもまたダライ・ラマ法王が亡命された結果生じたことなのです。
仏法を聴く前に正しい動機をもつ
さて皆さんは今日、仏法を聴くためにこの場に来られました。そこでまず大切なのが正しい心構え、正しい動機を持つことです。「なんの果報ももたらさない動機(lung ma bstan gyi kun slong )」、あるいは不純な動機を抱いて仏法を聴いてはなりません。仏法ってどんなものだろう、ちょっと覗いてやろうといった気安い動機で仏法を聴いても、それによって将来なんの成果も得られません。まず「なんの果報ももたらさない動機」を捨て去りましょう。
また今生の幸せを願って、今生で病気をしないよう、望まざることが起きないよう、さまざまな恐怖から身を守りたいといった「難から逃れようという動機」だけで仏法を聴くのも正しくありません。また有名になろう、名声を得ようという動機で仏法を聴聞するのも不純な動機といえるでしょう。
仏法を聴く際、抱いている動機によって人を上士・中士・下士の三種類に分けることができます。下士(凡夫)は地獄・餓鬼・畜生の三つの悪しき境地(三悪趣)の苦の恐ろしさを小耳にはさみ、怯え、そうした境地に来世落ちたくないという思いから仏法を聴きます。来世、自分ひとり三悪趣の苦しみから解き放たれたいと望む下士の動機は、清浄な正しい動機とはいえません。
中士(声聞・縁覚など自らのために悟りを求める人々)は、三界(欲界・色界・無色界)のいずれの世界も、苦楽があると悟っています。彼らは自分だけのために、三界の苦楽すべてから離れたいと願い、仏法を聴聞します。こうした中士の動機は中程度の動機であり、正しい動機とはいえません。
それでは仏法を聞くにあたって、どのような動機を持てばよいのでしょう。まず空のように無限に存在する衆生たちは、自分の前世で一度は父であり、母であったことがあると想起します。彼らは私の両親であったとき、私のためにあまたの苦労をしのび、私を養うために悪業をなし、その結果、八熱地獄や八寒地獄に落ちて暑さ寒さの苦しみや、あるいは餓鬼の世界に落ちて、飢えや渇きの苦しみを味わっています。動物に生まれたなら、無知におかされているゆえに、人に使役される苦しみを味わいます。六道輪廻の中のよりよい世界、人・阿修羅・天界に生まれれば、多少の幸福はありますが、この幸福は有漏(煩悩に汚れた)の幸福であり、無漏(煩悩がなくなった境地)の幸福でないため、たちまち失われてしまいます。一時の有漏の幸福ではなく、恒久につづく無漏の幸福を求めなくてはなりません。
上士(菩薩、つまり大乗仏教の修行の道を歩む人々)は生きとし生けるものを苦から救い、一時の幸福ではなく最終的な幸福に導こう、そのために釈迦牟尼仏が示された解脱と一切知の境地へと至る修行道を行じようという決意して仏法を聴聞します。あなたがたは上士の動機をもって仏法を聴かなくてはなりません。利己心からではなく、父であり、母である生きとし生けるもののために、つまり利他心をもって仏法を聴聞することが肝心なのです。
もちろん動機だけでなく、仏法を聴聞する皆さんの行動もまた大切ですが、これについては皆さん立派な方々ばかりでしょうから、申し上げるまでもないでしょう。
ギャセー・トメー・サンポについて
今日はギャセー・トメー・サンポの著した「菩薩の37の修行法」、これは37の詩句からなるテキストですが、そのなかのいくつかの詩句に基づいてお話をしたいと思います。
その昔、聖国インドよりパドマサンバヴァが雪国チベットに来られました。そしてトゥー地方を経て、シェー・グルチュという土地に至り、三種守護尊(金剛手・観音・文殊)の化身が出現すると予言をなされました。ギャセー・トメーはパドマサンバヴァの予言にあった観音の化身なのです。彼が観音の化身であるしるしに、人の考えもおよばないほど慈悲の心が深く、菩提心も篤く、彼の傍らでは、本来仲が悪いはずのネズミと猫も、犬と鹿などの草食動物も喧嘩をしなかったといいます。姿こそ仏画に描かれているものとちがっても(白い千手観音のような姿ではなくても)、本性はまさに観音菩薩そのものだったのです。
これが今回の教えの根本のテキストです。さらに私の根本のラマであるザトゥル・リンポチェが、このテキストの注釈書を記されているので、注釈書に基づきご説明していきたいと思います。
根本のテキストは37の詩句によって構成されていますが、この37の詩句は(1)前行にあたる仏教への入門部分と(2)本行にあたる上士・中士・下士それぞれの修行法の説明からなっています。(1)の前行部分を構成するのは1番目の詩句から7番目の詩句です。今回の法話では、1番目から3番目の詩句(仏教を修行するさい欠かせぬ条件である八暇十円満を見出すことは難しい、故郷をすてる、人里離れた場所に拠る)は省きます。
第四句――無常を想う
| 長い間交わってきた友とも別々に離れ 努力して得た財富も後に残し 意識という客が肉体という旅籠を発つ 今生を放棄するのが菩薩の修行である |
釈尊はサールナートで初めて仏法を説かれました。その時説いたのが四つの聖なる真理(四聖諦)です。釈尊は「苦を知りなさい」「苦の源を放棄しなさい」「修行の道に拠りなさい」「(煩悩の働きを)断ち切った状態に至りなさい」と説かれました。
「苦を知りなさい」とは四つの聖なる真理の最初のもの「苦にまつわる真理(苦諦)」を知れということです。これまで私たちはこの世が苦そのものであると理解できずにいました。それというのも、すべての事象が恒常である、実体をもって(自立して)存在していると信じ込んでいたからです。しかしすべての事象は独立してではなく、原因と条件(因縁)から成り立っており、それゆえ常に変化しています。私たちは無常という理に自らの心を馴らしていかなければなりません。無常の例
今皆さんはこの場に集まって仏法に耳を傾けられていますね。でもこれが終われば、みなそれぞれの家にもどって、この場もからっぽになるでしょう。これもまた無常です。ここにいらっしゃっている方々は、お年を召した方で60代、若い方で20代、30代でしょうか。でも今まだ若くても、時が移り行くにつれ、次第に老いて行きます。
| 生の末路は死 絆の末路は別れ 頂きをきわめれば、後はおちるのみ 築いたものも、最後に失う |
生まれたその日から、私たちは一日一日死に近づいてきます。母の胎内から出たその日から、私たちは死への道を一歩、一歩あゆみつづけるのです。死への道はまっすぐな道です。日本人はよく健康管理がなされているので長寿であると聞いています。でもいくら長寿を享受している日本の方でも百歳を越えて生きる人は少ないでしょう。人は日々、一歩一歩死に近づいていくのです。これまた無常のしるしです。
また夫婦の絆、両親の絆、師と弟子の絆といった人と人の絆も何時の日にかは切れるものです。これも無常の理のなせるわざです。
太陽や月を見てもわかるように、いったん天空の頂きにあがれば、あとは沈むしかありません。首相や大臣を務め、一時栄華を極めても、後に失墜して、中には刑務所入りする人も今のご時世よく見かけるようです。これまた無常の理のなせるわざです。
またいくら財富などを築いても、それが留まることはなく、いつかは失われるものです。
死
無常にまつわることで特に考えなければならないのが「死」です。無常の瞑想にもいろいろありますが、根本は以下の三つのです。
- 死は必ず訪れる。
これは確実なことであり、なんの疑問もありません。 - いつ死ぬか確実ではない。
ひとはすべて死ぬものだとわかってはいながら、それでも今日は死ぬまい、明日は死ぬまいと思いこんでいるものです。いざ死が訪れたとき、我々は不意打ちをくらったも当然でなんの準備もできていないのです。 - 死に際に役立つのは仏法だけである
いざ死がおとずれたら、金銀財宝などのこの世の宝がいくらあってもなんの役にも立ちません。いくら権力や財産があっても、何一つ役に立たず、バターの中から毛を引き抜くように意識がすっと肉体から抜け出ていくのです。
死の要因は無数にあります。今の時代、医療も発達し、よい病院や薬もあれば、手術もできます。しかし薬を飲んでもきかず、多くの人間が病院で死んでいくことも事実なのです。
今まで死ななかった人は一人もいません。肉体は因縁が集まって生じたにすぎません。賢い人も、博識の人も、地位の高い人も、みな死に行く運命にあります。権力をもっていても死から逃れられられません。釈尊でさえも、クシナガラで涅槃に入られたのです。パドマサンバヴァもまた不死の虹の身体を得て、サンドペルリ(銅色吉祥山=パドマサンバヴァのいる浄土)に赴かれ、この世にはおられません。インドからあまたの聖者や成就者が雪の国チベットに来られましたが、その誰も涅槃に入られ、今この世に残っていられる方は一人もいません。ただ伝記や歴史からそのような人々がいたと知ることができるだけです。
このようなことを思い巡らせ、自分のこの肉体がこの世に永久にとどまることはない、自分は必ず死ぬのだ、死に際に役立つのは仏教しかない、ならば私はこれから清浄なる仏法を行じようと決意するのです。このような考え方に心を馴らしていきます。自分はいつか必ず死ぬことを常に念頭においていなければなりません。
「釈尊の残された足跡は、象の足跡のごとく最高である、瞑想の中でも無常を瞑想するのが最高の瞑想である」といいます。象の足跡は犬のような他の生き物と比べるとは、比較にならないほど大きい、そのように釈尊の残された跡も限りなく大きいというのです。
また釈尊も「百回比丘にお食事を供養するより、一刹那無常を想起したほうが多くの功徳がつめる」と説かれているように、瞑想の中では無常という概念を瞑想するのが最もすぐれた瞑想なのです。こんな逸話もあります。ある弟子が師に「仏法を説いてください」とお願いしました。すると師は弟子に「手を出しなさい」と言い、弟子の手を握ると「私も死ぬし、あなたも死ぬ。私も死ぬし、あなたも死ぬ。私も死ぬし、あなたも死ぬ」と3回繰り返したのです。師はそれ以外、あとは一切仏法を説こうとしませんでした。弟子は無常の理を知って、瞑想し、悟りを得たということです。
このように無常ということが理解できれば、仏教を修行する動機も生じ、最終的には不死の境地をえることも可能なのです。死に際には役立つのは仏法のみ、これを忘れることなく、仏法の修行をするのです。
第五句――悪しき友を捨てる
| 交われば三毒(怒り・貪り・無知)が増大し 聞思修が衰え 慈しみの心とあわれみの心がなくなる 悪しき友を捨てるのが菩薩の修行である |
どのような友と交わろうとも、相手の身体・言葉・心の行為が自分の方に移ってくるものです。ですから、悪いお手本を示すような友達と交わるのはよくありません。それまで悪人でなかった人も、罪深い悪人と交わっていると、三毒(怒り・貪り・無知)が増大し、三慧(教えを聴いて生ずる智慧、それについて思いをめぐらして生じる智慧、瞑想して生じる智慧)が衰え、慈しみの心とあわれみの心がなくなっていきます。そのような悪しき影響をおよぼす悪しき友、罪深い師友とは手を切らなくてはなりません。悪しき師友や罪深い友人と交わっても、命を落とすことはありませんが、解脱への命が、一切知の境地へと至る道が閉ざされてしまいます。
師を選ぶ前に吟味する
仏法を聴き、それについて思いをめぐらし、瞑想することが、すなわち解脱への因となります。聞思修は解脱への命を守るのです。聞思修にも正しい聞思修と、誤った聞思修があります。正しい聞思修に拠らず、誤った聞思修に拠っても解脱の道を歩むことはできません。
今のご時世、宗教、あるいは仏法のごときものを説く人はたくさんいます。ですから、皆さんが師を選ぶ際には、師とするにふさわしい資格があるかどうか、前もってよく吟味する必要があります。師の資格のない人(悪しき師)であっても、仏法や聞思修について説くことも、ルン(口頭伝授)を与えることはできるのです。
悪しき師につくのは、毒の入った食べ物を摂るのと似ています。食べた瞬間にはそれなりに満腹するかもしれませんが、所詮、毒は毒です。体をやられて最後には死に至ります。パドマサンバヴァは「ラマを吟味しないのは、毒に触れるも同然」と述べています。このように師と崇める前によく吟味することが大切なのです。よくよく吟味して、納得した上で自らのラマとして受け入れ、教えを受け、それに従って修行するのです。
「修行僧たちの集まり(僧伽)は仏教の崇拝の対象とすべきである」と釈尊は説かれました。とはいえ善き友と悪しき友はよく区別しなくてはなりません。悪しき友と行動をともにすると、その潜在的な力(薫習)がこちらにも伝染してくる恐れがあるからです。
ドムトゥンバがアティーシャに「最悪の敵とはなんでしょう」と訊きました。するとアティーシャは「敵の中で最悪の敵とは罪深い(悪しき)友である。罪深い友と交わると、聞思修の智慧も得られないうちに、その罪深い友の考え方や行動が伝染してしまう」罪深い師友、悪しき友は伝染病に罹っている人ようなもので、交わるといつのまにか、その罪深い考え方や行為が移ってきてしまいます。伝染病に罹っている人がいれば、移るのではないかと怯えて逃げますよね。わざわざ伝染病に罹っている人のもとに行く人はいませんね。それと同様に罪深い友も避けるべきなのです。
第六句――善い師に従う
| 拠れば、欠点が良いものに変わり よき徳性が上弦の月のように満ちていく 正しい師友を自分の身体より 大切にするのが菩薩の修行である |
ラマ(師)に拠ることなく、自分勝手に経典を読んで自習しても、ある程度の知識は得られ、理解もできるでしょう。しかしラマから教えを直接受けるのは、経典を自習して、勝手に修行するのとはまったく異なります。正法というのは、釈尊より師から弟子、弟子からそのまた弟子へと師資相承で伝えられていくものだからです。師資相承の加持があるなら、聞思修を行じても、あるいは他人にアドバイスを与えても、大きな力をもちえます。ですから必ずラマに拠って、仏法の修行をする必要があるのです。自分勝手に修行してはなりません。
まったく見知らぬ土地に行く場合、その土地にくわしい人に案内してもらわなければ、道に迷ってうろうろするだけです。それと同様に仏陀の境地へといたる道を歩もうとするなら、その道に精通したラマに案内してもらわなければ、迷うだけです。
白檀という香木があります。普通の木の皮を白檀と一緒に長い間放置して置おくと、香りのなかったはず普通の木の皮にもいつのまにか白檀の馥郁たる香りがうつっています。同じように優れた師のもとに身をおき、師にならって聞思修に励み、修行をすれば、いつのまにか師のよき徳性が移ってくるものです。
商売を始めたばかりのものは、大商人のもとで見習をして商売について学んで経験を積んでいくのが商売を学ぶ正道です。そのように仏教を修行しようとするものは、よき師のもとで、聞思修を学ぶ必要があります。
逆の喩えをしましょう。悪臭放つ魚の骨を吉祥草(湿地に生える茅。釈尊が悟りをひらかれたとき、菩提樹の下でこの草を敷いていたという)と一緒にしておくと、もともと匂いなどなかった吉祥草に、いつのまにか魚の悪臭がうつってしまいます。このように不善の師や友と交わっているとその悪しき習性が移ってきてしまうのです。
ラマを吟味するポイント
ではよきラマとはどのような特性を備えているのでしょうか。どこを吟味するべきなのでしょうか。
「内タントラ」に「無知なのに慢心なもの、蒙昧なのに単語に拘泥するもの、他人の心をかき乱す言動を弄するもの、誤った道にいるもの、仏法を聴く事が少ないのに、慢心しているもの、師を吟味しないのは、弟子にとって魔である」とあります。
ラマの心に慢心が満ち溢れ、尊大きわまるならば、ラマのもつべき特性に反します。ラマ自身がさほどものを知らないのに、真の意味もわからないのに単語にやたら拘泥するのもよくありません。実際に手を下さなくても他人を傷つけるような言動を弄するもの、自身にさほどの教養もないのに、バラモン階級のように血筋や家柄を自慢するもの、さほど仏法を聴聞せず、聞思修も少ないのに、慢心しているもの、他人より優れていると思い上がっているもの、こうした人を師と仰いではなりません。
菩薩の種族は自分の徳性を見せびらかすことなく、隠しているものです。ところが普通の人々は自らの徳性を外にみせびらかすものです。腹の底では馬鹿にしながら、表面上は尊敬している様子をよそおい、おべっかを使うのは、その相手が徳性を欠いているしるしです。
ラマが備えるべき徳性
ならばよきラマが備えるべき徳性とはなんでしょう。まず怒らないこと、すなわち忍耐力があることです。忍耐力はすばらしい徳性です。それとは逆に怒りっぽく、驕慢なものはラマとしてのよき徳性を欠いています。仏たちはみな六波羅蜜行を成就した存在ですが、中でも特に弥勒(マイトレーヤ)は忍耐力に富んでいます。弥勒の身体はとても大きいのですが、それは弥勒の忍耐の徳性のあらわれであるといわれています。いくら善根を多くつんでも、それを一瞬のうちに失わせるのは怒りです。怒りがないのが善きラマです。
さらに一切の衆生が、苦と苦の因から離れることができるようにと願うあわれみの心と、幸福と幸福の因を持つことができるようにと願う慈しみの心をもっていること、これも大切です。慈悲心こそ根本とすべき徳性です。これを踏まえたうえで、よきラマはさらに四つの徳性を有していなければなりません。
- 広大なる教えを受けていること。顕教・密教の経典と論書、別解脱戒(比丘、比丘尼、在家信者の戒など)・菩薩戒・三昧耶戒(密教の戒)の大切さを理解し、経・律・論の三蔵に通じていること。
- 煩悩障(悟りへの障害となる煩悩のさわり)と所知障(知のはたらきの妨げなる微細な障害)という二つの障害をすべて捨て、知るべきことをすべて悟り、これら二つの徳性について、他人がなんら疑いの念を抱くことがない。
- ひとり子に対する母のように、生きとし生けるものを慈しむことができる。
- 一切の煩悩と解脱の特質が空性そのものであることを示すことができる
ラマへの拠り方
このようなラマに私たちは拠るべきなのです。これには心において拠るものと行動において拠るものの二つがあります。心において頼るのも
- 信心によるもの
- 恩を念じるもの
の二種類あります。経典にも「信心を前行の母のように生じせしめよ」と述べられています。信心は帰依の入口であり、ラマに拠るための入口でもあります。
三種の信心
信心にも三種類あります。希求の信心(’dod pa’i dad pa)、清浄な信心(dang ba’i dad pa)、堅固不壊の信心(mi phyed pa’i dad pa)です。希求の信心とは「自分にもよき徳性が欲しい、そのために信心をおこそう」と思うことで、信心の入口には足を踏み入れているとはいえ、最上の信心と呼ぶことはできません。特にすばらしい仏像や仏塔などに参拝したとき、尊敬すべき、優れたラマや師たちにお目にかかったとき、「なんてすばらしいのだ」という驚嘆の気持ちが自ずと生じるものですが、これが清浄な信心です。これもまた最上の信心と呼ぶことはできません。真の最高の信心とは堅固不壊の信心、もっとくだけた言葉でいえば信仰の信心です。堅固不壊の信心とは、よき徳性を備えたラマに対して、心の奥底から深い、不退転の信仰心をおこすことをいいます。
希求の信心や清浄な信心は信心の前行のようなものです。
ラマを仏とみなす
私たちは現実に仏や如来たちに出会うだけの功徳を有していません。ですからよきラマに出会ったときに仏の化身そのものであると、その徳性は仏の徳性そのものであると見なすのです。狩人サラハは野生動物を狩っていましたが、獲物の生きものは仏国土に生まれ変わっていました。漁師のティローパは魚を釣ってはそれを食べていましたが、獲物の魚は仏国土に転生していました。でも昨今ではこのような高い悟りに至った成就者はいないでしょう。もちろんサラハはごく特別な存在で、普通の狩人は生活のため、戯れのため、他の生きものを殺めているにすぎません。サラハは殺した生きもの意識をより高い境地にひきあげてあげていました。そこを間違えてはいけません。その昔インドにはサラハに代表されるような八十四人の偉大なる成就者がいました。
「大宝積経」にも「信心なき者に白い浄法が生まれることはない。炎で焼かれた種子に緑の芽が芽吹くことがないように」と説かれています。信心のない者に聞思修の智慧が生じることはないのです。
恩を念じる
二番目の「恩を念じる」についてお話しましょう。これまで過去にあまたの仏たちがこの世に生じました。だがその慈悲の心でさえも、私たち生きものを輪廻の苦しみの大海から護ることはできませんでした。それは私たちが自らの煩悩を四つの力に依って断ち切ることができなかったからです。また菩薩たちも無数に出現しましたが、その慈悲の心も私たちを輪廻から解き放つことはできませんでした。それ以外にも、インドには八十四人の成就者、雪の国チベットにも数多くの聖者が現れました。しかし私たちはそのような偉大な存在たちと出会う幸運には恵まれませんでした。
現代は五濁悪世(ごじょくあくせ)、つまり五つの汚れに満ちている時代です。五濁とは以下の五つです。
- 劫濁――戦争や飢餓や病気が増える時代の濁り
- 見濁――思想の乱れ
- 煩悩濁――煩悩がはびこる
- 衆生濁――衆生の資質が低下する
- 命濁――衆生の寿命が短くなる
これらの五濁が満ちている時代に、私たちは人として生まれる幸運には恵まれたものの、不善の行為ばかりなしています。にもかかわらず私たちは幸運にもラマと出会い、ラマから教えを受けることができたのです。私たちには八万四千の煩悩があります。せんじつめればこの八万四千の煩悩も怒り・貪り・無知の三毒にまとめることができます。これを対治するための方便としてラマたちは釈尊から伝わる八万四千の法を説いてくれます。これは仏たちから直接教えを受けているのと変わらず、自分にとってはラマとは仏をもしのぐありがたい存在なのです。
この世には千の仏が現れるといいます。しかし悪世ともなると衆生が心底堕落して教化することも不可能になるため、いかなる仏もこの世に現れようとはしないのです。その時率先してこの世に現れてくださったのが釈尊なのです。逆に未来仏の弥勒の時代ともなると、人々はあまりにも幸運に恵まれ、富と長寿を享受しているために、仏が出現しても教化することが難しいといわれます。その時にあえて衆生のためにこの世に現れるのが弥勒仏なのです。
ラマの徳性は仏たちに等しいと見なさなくてはなりません。そして恩深いとい点では仏たちをもしのぎ、はかりしれないものがあるのです。
行動を通じてラマに拠る
行動を通じてラマに拠るとは、三種の方法でラマが満足いくよう仕えることです(zhabs tog rnam gsum三種承事)。もっとも優れた仕え方は修行を供養すること(rab sgrub pa’i mchod pa)、中程度の仕え方は身体と言葉で仕えること(’bring lus ngag gi zhabs tog)、もっとも程度の低い仕え方は財を捧げることです(tha ma zang zing gi ‘bul ba)。
修行を供養する
修行を供養するとは、ラマの説かれた教えを苦難を乗り越え最後まで実践することです。チベットの偉大なる成就者ミラレパが師であるマルパに、インドの成就者ナローパがティローパに仕えた時のことを思い起こしてみてください。
ティローパはナローパに十二年間のあいだ仏法を説こうとせず、無視するか虐めるかしました。しかし結局はティローパの慈悲の心によって、ナローパは師と等しい高い悟りに至ることが出来たのです。昨今では時代も異なり、ティローパのように弟子に苦難をしいるラマもいませんし、ナローパのように苦難に耐えられる弟子も存在しようもありません。ともあれ喩えとしてあげればそのようなものです。
身体・言葉・心でラマに仕える
修行を供養できれば、身体と言葉において仕えることも、財を捧げる必要もありません。しかし修行を供養できないとなれば、身体・言葉・心においてラマに仕えるしかありません。これが中程度の仕え方です。身体・言葉・心において、ラマの下僕となってお仕えするのです。身体において奉仕し(ラマの部屋の掃除に至るまで)、ラマの言葉にはなんでも従い、仮にラマから叱責されてもそれに腹を立てたりせずに我慢し、叱ることによってラマが自分を教化しようとしているのだと思い、ラマが真実でないことを述べても、自分のためにわけあって嘘をついたのだとみなし、決して邪見などいだかず、感謝の念をもってひたすら尊敬するのです。ミラレパが師であるマルパから苛められながらもひたすら忍の字で仕えたと同じように、身体・言葉・心でラマに仕えるのです。
ミラレパはラマであるマルパに身体・言葉・心を捧げて仏法を説いてくれるようお願いしましたが、まったく教えを受けることができず、何年と月日が無駄にすぎていきました。
失望したミラレパはマルパのもとから逃げ出しました。しばらくしてミラレパの施主から「八千頌般若」を唱えてほしいとの依頼がきました。この「八千頌般若」の中には悟りへといたった菩薩たちがそれまでいかに苦難の道を耐え忍んだかの記述があります。これを読んだミラレパはこれまでの自分の努力など些細なものであったことに気づき、改心してマルパのもとに戻ったといいます。でも日本の人々はとても礼儀正しい人々ばかりですから、ラマへの尊敬の態度について、特に注意する必要もないでしょう。
財を捧げる
もっとも程度の低い仕え方は財を捧げることです。もちろん財を捧げようにもその財がなければが捧げようもないわけですが。しかし財産のある人の中には、自らの財を捧げるという形でラマにお仕えする人もいるのです。
昔のチベットにはこのような習慣もありました。夏場にラマは弟子に「氷が欲しい」と告げます。弟子は遠路はるばる氷探しに行きますが、当然みつからず、ラマに「ありませんでした」と報告します。逆に冬場に「花を持ってきなさい」と命じます。弟子は花を捜しに行きますが、冬場のチベットにそんなものがあるはずもないのです。しかしこうすることによって師と弟子の間には「えにし」ができたのです。
ラマに仕えることによって得られるご利益
このようにラマにお仕えしてどのようなご利益があるのでしょうか。仏の境地にたどりつくためには色身と法身というふたつの仏の身体を獲得しなければなりません。そこで修行という供養を行うことで最終的に法身を、身体・言葉・心でラマに仕え、財を捧げることによって最終的に色身を得ることができるのです。福徳と智慧をつみつくし、罪を浄化しつくすことで私たちは仏の境地にいたることができます。しかし、そのためにはその礎となるものが必要です。
ラマの喩え
ラマは喩えてみれば医師のようなものです。私たちはルン・ティーパ・ペーケン(人間の体内にあるとされる三体液。これらがバランスがとれていると健康が保てるが、いずれかが増えすぎたり減りすぎたりすると病気にかかる)こそ病んでいないものの、三毒を病んではいるのです。怒りという病気を病み、貪りという病気を病み、無知という病気を病んでいるのです。三毒からさらにさまざまな煩悩が、慢心や嫉妬などが生まれでてきます。ですからあなた方は病人のようなものなのです。ラマという医師は、怒りへの処方箋として慈しみの心を、貪りへの処方箋として不貪欲を、無知への処方箋として禅定の瞑想を説きます。ラマの説く正法は喩えてみれば病に効く薬のようなものです。
ただしラマにできるのは教えを説くことだけで、それを実践するのはあなた自身です。仏法を聴聞して智慧を培い、考えをめぐらして智慧を培い、修行することによって智慧を培うのはあなた自身です。ラマはそのための道をただ示されるだけです。あなたの煩悩を断ち切れるのはあなただけなのです。
ラマという医師が処方してくれた薬を飲もうともせず、病気の原因となっている日々の悪しき行動を改めようともしないなら病は治るはずもありません。逆に医師を信頼し、その忠告に従った行動をとれば、煩悩という病は癒えるでしょう。ラマは医師、正法は薬、自分は病人である、病気を治そうとする時と同じように修行に専念し、ラマに拠るべきなのです
四つの聖なる真理
釈尊は以下のような四つの真理を説かれました。
- この世が苦であるという真理を知りなさい
- 苦の源を断ち切りなさい
- 苦を断じた境地があるという真理
- 苦を断じるための道(を示すことができるのはラマあるいは善師だけである)
苦の源とは煩悩です。煩悩は、私たちの心に湧き上がってくるさまざまな妄念は八万四千種あります。釈尊は苦の源である八万四千の煩悩を断ち切るために、八万四千種の教えを説かれました。煩悩を断ち切ることができればできるほどあなたは高い境地へ赴くことができますし、逆に断ち切ることができなければ凡夫のままです。私たちの最大の敵とは、苦の源である煩悩です。先程アティーシャが「敵の中で最悪の敵は罪深い(悪しき)友である」とドムトゥンパに答えたというエピソードを披露しましたが、私たちの煩悩を引き起こすからこそ罪深い友は最大の敵なのです。
ラマに正しく拠るとは
このように苦を断じるためには師に拠らなければならないのに、弟子の方が、
- 資格を備えたラマに拠ることをしらず、
- 仮に知っていても、怠慢などが原因でラマに拠ろうとせず、
- ラマに対してしかるべき敬意をはらってラマのよき徳性を、ラマのよき考え、行動を学びとらなければならないのに、それができない、
- ラマが仏そのものであると念じるどころか、ラマも自分も同じ人、対等の存在であるとみなす、それどころか
- ラマを軽蔑して、ラマを侮蔑するような言葉を吐く
以上のような行為をしながら、高い悟りを求め、自分が高い悟りを得たという妄言を吐くようようでは、真の悟りに至るどころか、砂を絞って溶かしバター(油)を得ようとするようなものです。あるいは燃える火の中に決して蓮華の花が生えてこないようなのものです。

ドムトゥンパは師であるアティーシャにこんなことを訊ねました。「チベットには瞑想を成就したと主張するものが沢山いますが、悟りの智慧を生じたものは少ないのです。どうしてでしょうか」するとアティーシャは「あなた方チベット人は、ラマを凡夫と見なし、仏として見なそうとしない。そんなことでどうして悟りの智慧が生じよう」
またチベットのラマたちがアティーシャに両手をあわせて「アティーシャ、どうかなにか教戒をいただきたいのですが」と大声でお願いしたことがありました(というのは失礼な態度であるわけですが)。するとアティーシャは「ははは」と笑い、「私は目も耳もいいから、そんな大きな声で叫ぶ必要はないよ。教戒とはすなわち信仰である。信仰があれば教戒は自ずとくるものだし、信仰が欠如していれば、教戒は与えられはしない」
またある日アティーシャが弟子たちに「おまえたちの中で、もっとも高い悟りの智慧を成就したのは誰か見てみたい」といいました。アティーシャの弟子の中で最も瞑想に熟達していたのはゴムパワで、当人も「悟りと得たということでは私に敵うものはいないだろう」と優越感をもっていました。ドムトゥンパは「私はずっとインド人の師であるアティーシャの通訳をやり、弟子としてお仕えしてきたので、瞑想する暇などなかった。瞑想によって悟りの智慧という点では、私はアティーシャの弟子の中では最低にちがいない」
ところがいざ悟り比べをしてみると瞑想に専念してきたはずのゴムパワは悟りは最低で、ドムトゥンパが最高でした。
それについてアティーシャは「ドムトゥンパは私にひたすら仕えつづけたからだ。またドムトゥンパは私の前にネパールからやってきた導師スムリティに十二年間にわたって仕えていた。それによってドムトゥンパの罪は浄化され、13年目に悟りの智慧を得ていたのだ」と説明しました。
このように苦を断ち切った境地に至るためには、正しい道を示してくれる師が不可欠なのです。
三つの正しきもの
昨日も申し上げたように、仏法を聴聞する際には、正しい動機をもつことが大切です。輪廻の苦しみの大海のなかに漂っている無量の衆生を苦しみを離れた仏の境地に導こうという決意、広大なる心構え、菩提心をもってこの教えに耳を傾けてください。善行の大小は、心構え(動機)の大小にかかっているといにしえの聖者たちも述べています。
ロンチェン・ラプジャムパは「三つの正しきもの(dam pa gsum)を守らなければ、いかなる善根も功徳となりえない」と説かれました。「三つの正しきもの」とは以下の三つです。
- 前行としての正しい発心(sbyor ba sems bskyed dam pa)
- 本行としての正しい空性(dngos gzhi dmigs med dam pa)
- 本行のあとの正しい廻向(mjug sngo ba dam pa)
「前行としての正しい発心」とは、衆生の利益のみを念じ、利己的な心など片鱗もなく、ただ利他の心をもってこの修行をしようと(ここでは仏法に耳を傾けるなど)決意することです。二番目の「本行としての正しい空性」とは、修行を始めて終わるまで(今のこの状況では仏法に耳を傾けている間ということになりますが)、すべてのものは夢か幻のようなものであり、実体を欠いている、空そのものであると常に念じていることです。チベット語でdmigs medとは無所得(主観と客観の区別をしないこと)つまり空性を意味します。そしてまた夢か幻のように実体を欠いていることをも意味します。
本行によって得られる善根はごく些細なものです。この善根をどんどん増やしていくためには、廻向する必要があります。空に果てがないように、衆生もまた無量に存在します。この無量に存在する衆生を仏の境地に至らしめるために、自分が積んだこの善根を衆生にまわすのが廻向です。それでは何故この廻向を行わなければならないのでしょう。
廻向をしておかなければ、一瞬怒りの心を起こしただけで、これまで積んだ善根は失われてしまいます。また自分が良いことをしたと他人に言いふらしたり、宣伝したりしても、善根は失われてしまいます。「ああ、うまくいかなかった」と後悔の念に苛まれても善根は失われます。このように善根を失わせる四つの原因があるのです。この四つの原因を無効にするために、廻向を行うのです。一旦廻向してしまえば、善根が失われることはありません。これら「三つの正しきもの」を押えたうえで昨夜に続き教えに耳を傾けてみてください。
第七句――帰依
自身も輪廻の牢獄につながれている
(輪廻の中にいまだ留まる)世間の神々に
誰を護ることができよう
それゆえ誰を護っても欺くことのない
三法(仏陀・仏法・僧伽)に帰依するのが
菩薩の修行である
輪廻と涅槃を、苦楽を怖れないなら帰依は必要ありません。しかし私たちは輪廻と涅槃を、苦楽を怖れます。ラマ・ジクメはこのようなことを言っています。「輪廻世界の存在はみな輪廻世界を怖れ、そこから護ってくれるものを探している」と。未だ輪廻世界に留まっている世間の神々、梵天(ブラフマー)や帝釈天、あるいはツェンやギェルポといった神魔のたぐいは、大きな力を持っています。しかし輪廻世界の恐怖から護って欲しいといくら彼らに頼んでも、そして彼らの力がいかにすごくても、自身が輪廻から解き放たれていない以上、彼らに私たちを輪廻の恐怖から解き放つ力はありません。その場限りのご利益をもたらすのがせいぜいといったところです。
ならばいかなる存在が私たちを護ってくれるのでしょう。私たちを輪廻の苦海から救いだし、恒常なる幸福の境地(涅槃)に導いてくれる存在こそが私たちを護ってくれるのであり、こうした存在に、すなわち仏・法・僧の三宝にこそ帰依すべきなのです。
パドマサンバヴァも「輪廻世界の拠り所にいかに帰依しても、結局のところは欺かれる。しかし三宝という帰依処(帰依の対象)には欺かれることはない」とおっしゃられています。輪廻世界からいまだ解き放たれていない存在にいかに帰依しようと、護ってくださいとお願いしようと、彼らにはその力はありません。
彼らは最終的にはあなたを欺くでしょう。しかし三宝という帰依処は、今生でも来世でもあなたを欺くことはありません。欺くことがないということは、間違うことがなく、真正であるということです。ですから「欺くことなき三宝(bslu med dkon mchog gsum)」とも呼ばれているのです。
また「帰依なくして仏教の誓いを立てることはできない」ともいいます。仏教の誓いの基盤をなすものは帰依なのです。帰依なくして仏教の誓いを立てても、その血脈につながることはできません。修行の成果として一切知の境地に至ることができるのも、そもそも帰依が基盤としてあるからです。
ですから、苦そのものである輪廻を怖れ、三宝が真正であり、欺くことがないことを心の奥底から信じ、帰依の誓いを立てることが肝心です。
帰依の教えは三つに分かれています。
- 帰依の分類
- 帰依の仕方
- 帰依についてのアドバイスそして帰依をしたことによって得られる利益
まず 1. の帰依の分類からご説明しましょう。帰依の分類も二種類あります。
- 帰依の分類
- 帰依の因である信心のありかたの分類
- 帰依そのものの分類です。
1) 帰依の因である信心のありかたの分類
帰依の因である信心のありかたは三種類、これについては先日「ラマへの拠りかた」の項で説明しました。三種の信心とは希求の信心(’dod pa’i dad pa)、清浄な信心(dang ba’i dad pa)、堅固不壊の信心(mi phyed pa’i dad pa)です。この三種の信心の中で、帰依の際に必要なのは、堅固不壊の信心、 つまり信仰の信心(yid ches kyi dad pa)です。信仰の信心があれば、功徳をたくさん積むことができます。その昔、聖国インドに大功徳王というものがいました。この王はとてつもなく深い哀れみの心を持っており、人殺しなどをした極悪な罪人がいても、罰したりできない性格でした。大臣たちは罪人を処刑できなければ、国をきちんと治めることもできないだろう、しかし慈悲深い王に処刑をお願いしてもかなうまいと思い、仔を生んだばかりですっかり凶暴化している象のそばに罪人をつれていき、殺させようとしました。いきりたった象は罪人の体に鼻を巻きつけ、高々と持ち上げて、地面に叩きつけようとしました。そのとき、象は罪人が赤い衣服を身につけているのに気づき、比丘にちがいないと思ったのです。象は罪人を地面に叩きつけるどころか、そっと地面において、鼻で草をとって、罪人の体についた泥をぬぐったのです。驚いた大臣たちは、その話を王に伝えました。王は、象ですらも、仏・法・僧の三宝にこれほど敬意の念を払うのだと感嘆し、自身でもまた三宝に帰依し、信心をおこしました。帰依と信心によってさらに功徳を積んだ大功徳王はその後、世界の半分を支配する王となったといいます。
2) 帰依そのものの分類
これには(1)果の帰依(’bras skyabs)と(2)因の帰依(rgyu skyabs)の二種類があります。「果の帰依」とは、あなた方が仏・法・僧の三宝に帰依して、正法を行じた結果得られるものです。三宝に帰依し修行すれば、あなた方自身のなかに三宝の徳性が生じます。それがすなわち「果の帰依」です。今はもちろん三宝の徳性をもってはいません。もっていないからこそ、まず、「因の帰依」を学び、それを実践していくことが肝心です。
また上士の帰依・中士の帰依・下士の帰依の三種類に分けることができます。この三種は心がまえ・時間・対象の点においてそれぞれ違いがあります。
下士の帰依
地獄・餓鬼・畜生の三つの悪しき境地(三悪趣)の苦に怯え、来世によりよい境地、天界や人の世界に生まれ変わりたいという思いにかられて、仏・法・僧の三宝に信仰をおこし、帰依するのがすなわち下士(凡夫)の心がまえです。帰依はその時に限っていえば、自分が死ぬまで行えばよいのです。そして最終目的は天界(輪廻の世界から解き放たれていない天衆の世界)か人の世界に転生することです。あるいは自分の人生に障害をもたらしている病気や魔物を追い払うことができるまで帰依すればよいのです。帰依の対象はもちろん仏・法・僧の三宝ですが、仏といっても仏像や仏の姿を描いた仏画や、比丘や仏教修行者といった目に見えるものに対して帰依します。
異教徒であっても、幸福を願い、善なる教えにしたがって修行をすることはあります。しかし異教徒は仏・法・僧の三宝に帰依することはありません。仏教徒と異教徒を区別するのは、三宝への帰依があるなしにかかっています。三宝への帰依があれば仏教徒ですし、なければ異教徒です。
中士の帰依
中士は輪廻の世界の一切の苦しみから解き放たれ、涅槃寂静の境地に至ることを望んで帰依を行います。時間の観点からいうと、その場に限っていえば死ぬまで帰依すればよいのです。最終目的は阿羅漢の境地を得ることです。
かれらにとって仏は道を示してくれる存在、仏法は道であり、僧伽(仏教の修行者たちの集まり)は道を一緒に歩んでくれる友達です。
下士と中士の帰依は小乗仏教の帰依です。ともに利己的な目的で帰依しているのであり、利他的な目的で帰依しているのではありません。しかし私たちは下士や中士ではない大乗仏教の帰依を行う必要があるのです。
上士の帰依
大乗仏教の顕教と密教の帰依のおおもとはあわれみの心です。それも信心のあるあわれみの心です。つまり衆生へのあわれみの心と三宝への信心の両方が兼ね備わった帰依を行うのが上士の帰依です。帰依をする際にも、利己心ではなく利他心のみでおこないます。空のごとく無限に存在する衆生たちはみな自分の父であり、母である。この父母なる衆生は苦の大海のなかにある。「私はこの衆生たちを地獄・餓鬼・畜生の苦から、輪廻の苦から救い、仏の境地に導こう」、こういった心がまえで三宝に帰依するのが上士の帰依なのです。
利己心に基づく下士の帰依と中士の帰依は、言ってみれば小心者の帰依です。上士の帰依は、利他心に基づき、あわれみの心と信心の両方を兼ね備えていなければなりません。時間という観点からいえば、上士は仏の真髄を、つまり菩提(悟り)を得るまで、仏の境地に至るまで、帰依し続けます。
上士の帰依の対象にも通常のものと、特別なものがあります。そこで三宝とはなにかをまず知っておく必要があるでしょう。
三宝とは何か ― 仏
その昔お釈迦様がまだ悟りを開かれる前、ただの人間だった時に、以下のような誓約を立てられました。生きとし生けるものが仏の境地にたどりつくまで、五位(修道上の位を五段に分けたもの)と菩薩の十地(悟りに至るまでの菩薩が修行すべき十の階位)を精進しよう、その間、決して利己的な行動に走ることなく、ひたすら他の生きもののためにつくそうと。彼はひたすら罪や障害を浄化し、福徳と智慧という二つの資糧を積み、聖国インドのブッダガヤに至って、菩提樹の木の下で座し、禅定に入られました。そして消滅変化を離れた永遠の智慧に真に出会われ、五智と四身を得られて悟りを開かれました。これがすなわち「(仏法を)お示しくださる無上の仏(という)宝」です。
チベット語のston paは「示す」、あるいは「説く」ことを意味しますが、お釈迦様が何を示したのかというと、苦楽の源を、善行をなせばその果として幸福を得、悪業をなせばその果として苦をえるという真理を、そして菩薩の道を示されたのです。お釈迦様が説かれた修行の道は真正なものであり、決して誤りはありません。
三宝とは何か ― 仏法
三宝の二つ目はダルマ、つまり仏法です。釈尊は生きとし生けるものの心のありかたに応じて八万四千の法門を説かれました。この八万四千の法門によって教理(lung)と証悟(rtogs pa)を示したのです。教理に属するのが経・戒・論の三蔵です。証悟に属するのが戒律・禅定・智慧の三学です。
「お護りくださる無上の仏法という宝」というからには仏法は私たちを護ってくれる存在であるわけです。仏法を実践することによって、私たちは輪廻世界のさまざまな苦しみから護ってもらえます。仏法とは、無上の護り手であるとともに、決して誤りを犯さないものなのです。しかしそのためにはまず私たち自身が仏法を実践しなければなりません。
釈尊自身も「仏法を実践しなさい」とおっしゃられています。いくら釈尊のお傍にあり、仏法を聴聞していても、それを実践しなければどうにもなりません。ちょうどデーヴァダッタと善星比丘(legs pa’i skar ma)がそうであったように。デーヴァダッタは釈尊のいとこでした。善星比丘は釈尊と同じくらい三蔵に通じていましたが、いっこうに修行をしようとはしませんでした。この二人は真理を説いた教えを無数に聴聞しながら、まったく実践しようとせず、釈尊に対して邪見をおこし、反逆しました。実践することで仏法はあなた方の護り手になってくれるのです。
仏法とは薬のようなもの、病気にかかったあなたを適切に治癒してくれます。
三宝とは何か ― 僧(僧伽)
次は僧(僧伽=修行者たちの集まり)です。釈尊が入滅して久しいのに、いまだ仏法が保たれているのは僧伽があるからです。梵天や帝釈天、大自在天、日神、月神など輪廻世界にいる高次の神々は大勢います。しかしこうした神々が仏法を伝えてくれるわけではないのです。釈尊が真理を示してくれる人であることを信じ、仏法とは私たちを苦から護ってくれるものであると信じるのが僧(僧伽=修行者たちの集まり)です。
さきほど仏法にも教理(lung)と証悟(rtogs pa)があると述べましたが、教理は師が弟子に仏法を仏教哲学の観点から解き明かすこと、証悟は修行においてのみとらえることができるものです。これは別名「説法をきくこと(bshad pa)」「修行すること(sgub thabs)」とも呼ばれます。今この場所に仏法に耳を傾けるために集まられた方々は、まだ仏・法・僧の三宝そのものとはいえません。しかし仏法僧の三宝の後を追う存在なのです。
仏の本質
三宝の一つ、仏の本質とはなんでしょう。煩悩障・所知障などすべての障害を浄化しつくし、悟りの智慧をすべて得つくした存在が仏です。チベット語では仏のことをサンギェー(sans rgyas)と呼びます。煩悩障と所知障の二つの障害の闇を浄化し(=サン)、二慧、つまり一切智と一切種智(あらゆるものの個別性を知り極める智慧)を完成させた(ギェー)存在が仏なのです。
仏の身体・智慧・御業
仏も身体、智慧、御業の三つの観点から見なくてはなりません。
仏の身体は二つ、法身と色身です。すべての生きものの心には如来の種子が、仏がすでに備わっています。その心の本質は、本来清浄(ye nas dag pa)です。しかしその心は、一時の汚れで覆い尽くされているため、仏に離れず衆生の段階にとどまっているのです。もしこの一時の汚れを完全に浄化できれば、衆生は法身を得ることができるのです。
法身は不動であり、形なきものであるため、そのままでは衆生とかかわることはできません。いまだ心を浄化しつくしていない衆生たちに、仏たちが自らを示すためにとる身体が色身です。例えば、菩薩たちに対しては色身のなかの受用金剛(報身)の姿を見せますし、普通の衆生に対しては色身のなかの変化身を示します。つまりいまだ不浄なあらわれを見ているものたちには 変化身を、清浄な表れの中にあるものには報身を示すのです。
仏の智慧は法界体性智・大円鏡智・平等性智・妙観察智・成所作智の五つです。
また仏の御業とは、子供も同然の衆生たちが無明の闇のなかにあることに慈悲の心を起こされ、その無明の闇を祓い、仏の境地に導くことです。仏はサンスクリット語でブッダといいます。身体と智慧の本質を究めたものといった意味です。
仏法の本質
煩悩障と所知障を取り除くための方便を示すのが、仏法です。
仏教では悟りの智慧のさまたげになる四つの障害を説きます。カルマの障害、煩悩の障害(煩悩障)、智慧の障害(所知障)、薫重(くんじゅう)の障害です。しかし、障害のなかでも基本となるのは、やはり煩悩障と所知障です。
ちょうど病人が病気を治すために薬を飲むように、衆生は煩悩という病から回復するために仏法という薬を飲むのです。
先ほど、仏法にも教理(lung)と証悟(rtogs pa)があり、教理に属するのが経・戒・論の三蔵だといいました。証悟とは、四つの聖なる真理のなかの滅諦(苦の滅した状態、涅槃にまつわる真理)と道諦(涅槃にいたる修行の道にまつわる真理)とかかわる教えです。特に戒律・禅定・智慧の三学は道諦と深くかかわっています。戒律・禅定・智慧の三学を修して、様々な障害を浄化したところで、滅諦へと到るのです。
僧伽(修行者たちの集まり=僧)の本質
ならばの僧伽の本質はなんでしょう。僧伽の本質は智の活動(rig ‘phrul=智の変化へんげ)です。法性の真義が智(rig pa)です。法性の真義である智(リクパ)を修行を通じて、自分の心の中に生みだすことができるなら、それが智の活動、智の変化(へんげ)となるわけです。
僧伽とは、善なる正道に私たちを導き、私たちのなかの教化されていない部分を教化してくれる存在です。
僧伽を分類すると、小乗仏教の声聞の僧伽と、大乗仏教の菩薩の僧伽の二種類あります。さらに小乗仏教の声聞の僧伽にも、凡夫と聖者の二種類があります。
小乗仏教の修行者たちの修行の道は、(1)資糧位(2)加行位(3)見道位(4)修道位(5)無学位の五段階ですが、資糧位と加行位の段階にあるものは凡夫で、見道位と修道位に至ったものが聖者です。
大乗仏教の修行者たちの修行の道は、まず資糧位と加行位の段階で菩提心を起こし、六波羅蜜行を行じます。この段階の修行者は凡夫です。しかし、見道位には入り、さらに菩薩の一地(歓喜)から十地に至るまでの段階にいるものは聖者となります。
僧伽とはサンスクリット語でサンガ、つまり集まりを意味します。僧伽の徳性とは、戒律を守り、禅定を行うなど、煩悩に汚されていない修行道にいるもののことです。修行の道に入っていないものはいまだ煩悩に汚れた道にあります。
以上が大乗仏教の顕教における帰依処である三宝の本質と長所です。
密教の帰依処
密教では顕教とは別の三つの帰依処を説きます。密教における三つの帰依の対象は師(ラマ)・イダム(守護神)・ダーキニーです。顕教の通常の帰依処にあてはめれば、ラマは二身(色身と法身)と五智そのものである仏にあたります。自分の根本のラマからさかのぼって、仏へといたるラマたちの血脈も、仏の化身とみなすのです。
イダム(守護神)について述べますと、密教では四種類のタントラがあります。この四種類のタントラに対応する守護神がいるのです。四種類のタントラとは、(1)所作タントラ(2)行タントラ(3)ヨーガタントラ(4)無上ヨーガタントラです。密教を六種類のタントラにわける場合もあります。その場合(1)所作タントラ(2)行タントラ(3)ヨーガタントラの三種類に(4)の無上ヨーガタントラを父タントラ・母タントラ・不二タントラに分けた三種類を加えます。
顕教の帰依処で僧伽にあたるのがダーキニーです。ダーキニーにも三種類、地から生じたダーキニー(zhing skyes kyi mkha’ ‘gro)とマントラのダーキニー(sngag skyes kyi mkha’ ‘gro)と倶生のダーキニー(lhan skyes kyi mkha’ ‘gro)が存在します。地から生じたダーキニーとは三つの聖地に住するダーキニー(あるいはダーカ)たちです。三つの聖地とは、一般にチベットの聖地であるツァリなどを指しますが、別にチベットには限りません。日本であれ、アメリカであれ、聖地ならどこでもいいのです。倶生のダーキニーとは私たちの心の本質である空性のことです。
ここで帰依について簡単にまとめてみましょう。
- 三宝の素晴らしい徳性の数々について理解します。
- これを知った上で、実際に三帰戒を受けます。
- 大乗仏教の帰依なので、菩提にいたるまで、智慧の真髄を悟るまで、つまり悟りを開くまで帰依の誓いを守り続けます。
- また自分でも「ラマに帰依いたします、仏に帰依致します、仏法に帰依いたします、僧伽に帰依いたします」という帰依文を唱え続けなくてはなりません。
帰依文の短いものはこのようなものです。
| 「師(である仏宝)に帰依いたします。仏・仏法・僧伽に帰依いたします。ラマ・イダム(守護神)・ダーキニーに帰依いたします。自身の心(は)・空にして澄明・(すなわち)法身に帰依いたします」 |
ここには外なる帰依・内なる帰依・秘密なる帰依がまとめられています。仏・仏法・僧伽に帰依するのが、外なる帰依です。ラマ・イダム(守護神)・ダーキニーに帰依するのが、内なる帰依です。自身の心(は)・空と澄明・(すなわち)法身に帰依するのが秘密の帰依です。自分自身の心は、空(ston)なる部分と澄明(gsal)なる部分からなっています。空なる部分がすなわち法身です。澄明なる部分が報身です。空なる部分と澄明なる部分の両方をかねそなえたものが化身です。これをゾクチェン用語で「本質は空(ngo bo ston pa)、自性は澄明(rang bzhin gsal ba)、慈悲は双入(thugs rje zung du ‘jug pa)」と言います。
帰依のアドバイス
帰依のアドバイスにも通常のアドバイスと特別なアドバイスがあります。通常のアドバイスは、
(1)行ってはならないこと(dgag bya)
(2)行うべきこと(sgub bya)
(3)倣うべきこと(cha mthun)の三つからなっています。
- 三帰戒を受けて、行ってはならないこと
仏にいったん帰依したら、いまだ輪廻の世界にとどまっている世間の神々、外道の神々である大自在天や、ギェルポ、ツェンといった神魔たちに帰依し、礼拝してはなりません。いまだ輪廻の世界にとどまっている彼らは、私たち生きものを輪廻の恐怖から守ってくれる力を持っていないからです。ダライ・ラマ法王は特に、いまだ輪廻の世界にとどまっている世間の神々には決して帰依しないよう、強くアドバイスなさっています。
仏法にいったん帰依したら、宝のごとき貴い身体を持った人間から些細な虫にいたるのまで、どんな生きものでも傷つけてはいけません。心においては他の生きものに対して悪い心を抱かず、また身体を用いて他の生きものを傷つけるような行為、例えば殴ったり 苛めたりといった行為をしてはいけません。他を傷つけるような考え、行為ともに避けるようにしてください。
また僧伽に帰依したら、外道や、罪深い人間と付き合ってはいけません。といっても、そうした相手に嫌悪の表情をみせろということではなく、一緒に行動しないほうがよいということなのです。なぜならば、罪深い相手とともにあると、その見解や考え方や行動パターンなどが移る可能性があるからです。つまり罪深い相手とは表面的な付き合いにとどめたほうがよいのです。
あなた方は大乗仏教徒として、すべての衆生が自分の父であり、母であることを知りました。ですから、父母である衆生に対して憐れみの心をおこさなくてはなりません。罪深い者でも、外道でも、ギェルポやツェンといった神魔であっても、いまだ輪廻の中にとどまり、さまざまな苦しみを味わっている衆生のひとりです。彼らに対しても憐れみの心をおこすべきなのです。 - 三帰戒を受けて、行うべきこと
仏にいったん帰依したならば、仏像や仏画の良し悪しを問わず、それが本物の仏であると思って敬意を払わなくてはなりません。たとえ仏像の全身がそろっていなくても、たとえ頭部だけでも、それが仏自身であるという概念をもって、高い場所に祀り、前で礼拝し、供物を捧げ、常々に気を使って、尊敬の念をあらわすようにしなければなりません。もちろん仏像は仏そのものではありませんが、そこに仏が宿られていると念じ、しかるべき敬意を払うのです。
仏法にいったん帰依したなら、釈尊の言葉をしるした経典、仏教学者たちの論書などは仏法そのものであると思い、高い場所におき、礼拝し、供物を捧げ、しかるべき敬意を払わなくてはなりません。経典の頁がすべてそろっていないものでも、たとえ経典の紙がやぶれて断片しかない、一文字しか記されていない紙でも、そこに仏法が宿っていると思い、決して粗末に扱ってはいけません。
仏像や経典はなるべく高いところにおくのがよいのです。チベット人は経典を運ぶ際も、右肩にのせて運びます。
仏教の習慣では、貴い存在に敬意をあらわすには、からだの右側を向けるか、それを右回りします。ですから、経典を左肩にのせて運ぶのは失礼にあたるのです。経典を地面に置くなどもってのほかですし、末席に置いたり、経典や仏像を売って金儲けをするのもいけないことです。
その昔、インドでは白、緑、青といった色は俗人がまとう衣の色で、比丘たちは赤や黄色の衣をまとっていました。ですからいったん僧伽に帰依したなら、赤や黄色の衣にはしかるべき敬意を払わなくてはなりません。その昔、チベット古代王朝の護教王ティ・レルパチェンは、自分の編んだ髪に紐をむすび、その紐の逆の先端に一枚の布を結び付け、その布の上に比丘たちを坐らせたといいます。王はこうやって比丘への信仰心を表したのでした。
アティーシャの一番弟子であったドムトゥンパは、仏教に精通した人物でしたが、比丘にはならず、居士(在家信者)のままでした。三宝のなかの僧伽に対して敬意をあらわすため、あえて在家信者の立場にとどまったのだといわれています。レティンがまだ幼く、沙弥であったとき、在家信者の姿をしているドムトゥンパがそれほどえらい人間であることを知らず、わたしの衣をもってきなさいと命じたことがありました。ドムトゥンパは僧伽への敬意をあらわすために、衣を手で捧げ持つのも失礼だと、わざわざ右肩にかけて、レティンのところに衣を持っていったといわれています。 - 三帰戒を受けたら、倣うべきこと
いったん三帰戒を受けたら、仏法僧の三宝の徳性に倣うべきです。
ラマや善友の考え方や行動をお手本として、ラマの教えに耳を傾け、仏や菩薩たちの教えを記した経典をよみ、その内容について考えをめぐらすことが肝心です。
結論を申し上げると、三帰戒を受けて何よりも大切なことは、他の生きものに危害を加えないことです。単に危害を加えないというだけでなく、危害を加えようという心を根本から断ち切ること、そうした心を作り出す原因から断ち切ることが肝心です。これぞ帰依にまつわるアドバイスの根本をなす教えです。
帰依にまつわる特別のアドバイス
これはガリ・パンチェン(1487年~1543年)の著作のなかに、アティーシャの言葉として記されているものです。
- 命をかけても帰依の誓いを守る
もし三帰戒を守り続けるならおまえを殺してやる、だが帰依の誓いを破るなら、おまえを庇護し可愛がってやろうなどといわれても、そのような脅かしに決して耳を傾けることなく、命をかけて三帰戒を守らなくてはなりません。 - 自分が病人であることを知る
顕教密教いずれの教えを修するにしても、まず自分が病人であると思わなくてはなりません。仏法僧の三宝は、病人である私たちに病気を癒す効果のある薬を示し、その薬を下さいました。私たちは仏法僧のあとを追い、病を癒す薬を自分自身で飲まなくてはならないのです。 - 縁起のよい日には、より熱心に帰依の誓いをたてる
チベット暦の1月15日は大神変化祭(cho ‘phrul dus chen)、釈尊がその神通力で、魔物や外道を制圧したことを祝う祭りです。チベット暦の4月15日は「サカダワ」は、釈尊がお生まれになり、悟りをひらかれ、涅槃に入られた記念日です。チベット暦の6月4日は初転法輪、釈尊が初めて仏法を説かれた記念日です。またチベット暦の9月22日は釈尊が兜率天からくだった記念日です。このような釈尊にまつわる記念日やチベット暦の15日(満月)、30日(新月)、8日は吉祥の日とみなされているので、こうした日を選んで特に三宝を念じ、三帰戒を受け、なるべく多くの善行を積むとよいでしょう。食べ物や飲み物を三宝に供養し、仏像などはあらたな衣を献じます。ちなみに密教の修行者にとって縁起のよい日は、10日と25日です。 - 自身で三帰戒を受け、それを守るだけでなく、他人にもそれを薦める
また、自分自身で三帰戒を受け、それを守るだけでなく他人にも三帰戒を受けるよう、また帰依のアドバイスに従って、行ってはならないことの数々を放棄し、行うべきことを行うよう説いてきかせます。 - どこへ行っても三宝を礼拝する
どんな場所へ行っても、三宝を礼拝し、三宝を倣い、三宝を供養し、三宝の徳性と慈しみの心を念じます。
昨今では帰依処である三宝をあまり大切にしようとしません。火山の大噴火や、大地震や台風の発生といった、地水火風の恐怖が襲ってくるのも、帰依処である三宝を大切にしないからです。
帰依のご利益
帰依することによって得られる功徳、ご利益の大きさは、空や海の大きさをはるかに凌ぐといわれています。沙弥戒や比丘戒といった出家者の戒を受けなくても、三帰戒を受けて修行すれば、あなたは在家信者(居士)になることができるのです。そして三帰戒は、仏教のすべての戒の基礎をなすものなのです。
三帰戒を受けたご利益にも一時のご利益と究極のご利益があります。
一時のご利益
帰依することで、今生でもさまざまな障害に遭わず、病気にもあまりかからず、長寿を享受し、過去のカルマや罪を浄化し、多くの功徳をつむことができます。また来世において、外道や野蛮人の世界に転生することもなくなります。また三宝のご慈悲により、地獄・餓鬼・畜生の三つの悪しき境地に転生しなくてすみます。また種々さまざまな仏教の戒の基礎と、徳性の基礎を築くことができます。帰依を充分に行えば、人の身体を持たない神魔も、あなたに危害を加えることはできません。ですからわざわざ守護の輪を観想する必要もなくなるのです。
究極のご利益
最初に帰依にも因の帰依と果の帰依があると言いました。三宝に帰依し続け、その行が究極に至れば、その結果として自分自身のなかに三宝の徳性が生じ、輪廻の他の生きものを救済する力も生じます。これが帰依の究極のご利益です。
アティーシャと帰依の教え
その昔、チベットの古代王朝の王ランダルマは出家者に 嫉妬するあまり破仏を行い、チベットの仏教はすっかり衰えてしまいました。その後、西チベットの王家のイシェー・ウーとチャンチュプ・ウーの尽力によって、インドのヴィクラ マシーラ僧院に住していた学僧アティーシャをチベットに招請し、それによってチベットの仏教復興にはずみがついたのです。チベットにやってきたアティーシャは、不純なものが混じったチベット仏教を浄化しました。アティーシャは仏教の基礎となる帰依がいかに素晴らしいかを説き、帰依の教えばかり授け続けたため、ゲシェー・キャムドゥワ(帰依 博士)の渾名がついたほどでした。アティーシャ自身は経・律・論の三蔵に通じた学者であり、またへーヴァジュラの化身ともいわれたほど密教に精通したヨーガ行者でしたが、84000の教えのなかで、帰依ほど尊い教えはないとして、密教の教えは秘して、ひたすら帰依のみを教え授けたのです。
今なおチベットのニェタンには、アティーシャのお堂であるドルマ・ラカンがあります。このお堂は文化大革命の際、中国人の手によって危うく破壊されるところでしたが、バングラデッシュ政府が介入してくれたおかげで(アティーシャはベンガル人で現在のバングラデッシュの出身となる)ようやく破壊されずに済んだのです。
帰依に精進すれば、病や魔物の障りに遭うことなく、死後も地獄・餓鬼・畜生といった三悪趣に生まれ変わるおそれはなくなります。さらに将来仏の境地を得るための因となるのも帰依の行なのです。
上士・中士・下士の帰依
帰依をするなら、自利のために帰依するのであってはなりません。独覚乗や声聞乗の帰依ではなく、大乗仏教の帰依を行えば、仏の境地に至るための速やかな道に入ることになります。
帰依にも上士の帰依・中士の帰依・下士の帰依がありますが、時間があまりないので、ごくさわりだけ述べましょう。
下士の帰依
来世を三悪趣に生まれることを怖れて、帰依を行うのが下士の帰依です。地獄には紅蓮の炎で焼かれる八熱地獄や凍るような恐るべき寒さに苦しめられる八寒地獄の苦しみがあります。こうした地獄に転生する原因は三大煩悩の中のひとつ怒りの心です。餓鬼の世界に転生する原因は貪りの心を起こしたことです。私たちは一日食べずにいるだけでも、腹が減ってどうしようもなくなります。しかし一旦餓鬼の世界に転生したなら、一生かけても食べ物を見つけることが出来ず、ようやく水を見つけたと思ったら、水ではなく血や膿だったという苦しみを味わいます。畜生(動物)の世界の苦しみなら、私たちがこの目で見て知っています。三大煩悩の中の無知が原因で私たちは畜生に転生するのです。こうした三悪趣の苦しみを知ることが、下士の修行の入口ともいえるのです。
お釈迦様は初転法輪の際に四つの聖なる真理(四聖諦)を説かれました。その最初のものが、苦にまつわる真理です。ならばこうした苦の原因はどこにあるのでしょう。苦の因は、自らがおかした不善の行為です。不善の行為の代表的なものが、十の不善の行為です。十の不善の行為とは――
- 殺生
- 盗み
- 邪淫
— これらは身体においておかす不善の行為です。 - 嘘
- 両舌(仲たがいさせるようなことを言う)
- 悪口
- 綺語(戯言をいう)
— これらは言葉においておかす不善の行為です。 - 貪りの心を起こす
- 危害を加えようという心を起こす
- 邪見を起こす
–これらは心においておかす不善の行為です。
身体や言葉の不善の行為に比べると、心による不善の行為は最も悪しき行為です。邪見は三煩悩の中の無知に起因するもので、因果法則も仏の境地もないなどと主張することです。邪見は心のおかす不善の罪の中でも最も悪いものと言えます。
これら十の不善の行為をおかした結果、私たちは三悪趣に生まれ変わるのです。
三悪趣の苦しみを知り、それを幾度となく想起するうちに、輪廻の世界から脱しようという決意(出離)が生じます。この決意が生じたところで、正しい修行の道に入ることが できるのです。これまで私たちは輪廻の世界から脱出しようという決意(出離)がなかったがゆえに、菩提(悟り)の境地を得ることができずにいたのです。この決意を得るための方便として、三悪趣の苦しみを知るのです。
カタムパの善知識(高い徳性を備えた人)ランリタンパ(glang ri thang pa 1054年1123年、ポトワの弟子で、「心を訓練する八つの詩頌」などを記した。1093年にランタン僧院を建立)は、三悪趣の苦しみを瞑想するあまり、一度を除いて生涯笑うことがなかったといいます。一度だけ笑ったのは、マンダラの中にあるトルコ石を2匹のネズミが取り合いをする姿を見た時だけでした。このように三悪趣の苦しみを瞑想すれば、輪廻世界から 脱出しようという決意が生じるものなのです。十の不善を制止するのは、十善です。
十善とは――
- 生きとし生けるものの命を救う>
- 執着を捨て布施をする
- 邪淫をおかさない
— 以上三つは身体において行う善なる行為です。 - 嘘をいわず真実を語る
- 人の仲を取り持つことをいう
- 人の徳性を褒め称える
- 意味のあることをいう
— これらは言葉において行う善の行為です。 - 貪りの心を起こさない
- 危害を加えようという心を起こさない
- 邪見を起こさない
— これらは心において行う善の行為です。
来世、人や天界の住民に転生することを期待する下士(最も低い動機をもって修行する人)は十善をなしていくようにしなければなりません。
中士(中程度の動機をもって修行する人)は、それに加えて、止観や禅定を行い、心の本質に住する修行を行うことで、声聞や独覚の悟りの境地である阿羅漢の境地に至ることができます。
ただ私たちは上士(最高の動機をもって修行する人)の道を、菩提心の基づく修行の道を歩む必要があります。菩提心にも世俗の菩提心と究極の菩提心の二つがあります。世俗の菩提心を起こす方法のひとつが、マイトレーヤから アサンガに伝えられた「因果の七つの教誡」です。「因果の七つの教誡」の各段階をおって修行することで、私たちは世俗の菩提心を得ることができます。
「因果の七つの教誡」とは――
- 生きとし生けるものを母と知る
- その恩を知る
- その恩に報いようと決意する
- 慈しみの心
- 大いなるあわれみの心
- 増上意楽(大いなる利他の心)
- 菩提心
また究極の菩提心は、止観の瞑想によって得ることができます。
自己愛を捨てる
大乗仏教の修行をするさい、最も大切なことは、自己愛を捨てることです。私たちは自分をこよなく大切に愛し、大切にします。私たちはこうした自己愛を捨て、他者を慈しむことをおぼえなくてはなりません。ランリタンパの「心を訓練する八つの詩頌」の中に
| 他人が嫉妬から ののしり、あざけるなど私を酷い目にあわせても 自らあえて負けをひきうけ 勝利は他人に捧げることができますように |
という一節があります。こうした修行をすることで菩提心が生じるのです。
帰依にまつわるアドバイスをまとめると以下のようになります。小乗仏教の帰依にまつわるアドバイスの基本は「他の生きものを傷つけてはならない」です。大乗仏教の帰依にまつわるアドバイスは「利他行をなせ」です。
利他の心があるならば、一見不善の行為にみえても、善の行為となります。さらに密教の帰依もあるのですが、それについてはまたの機会にしましょう。