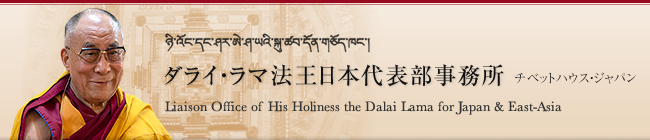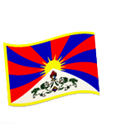2002年5月27日 シドニー・モーニングヘラルド
ダライ・ラマ一行は、今朝になって沖に向かって出発した。質素だが知恵のあるダライ・ラマの言葉を傍聴しようと、これまでの9日間、スタジアムやエンターテイメントセンターには約11万人のオーストラリア人が詰め掛け、多数の人々が、この体験を通して人生が豊かになったと感じているようである。
チベット人指導者ダライ・ラマは、精神な力を渇望している西洋文化について多くのことを述べ、幸福と内面の安らぎを得るための簡単な方法を率直に語る。
しかしながら、彼のメッセージの中心にあるものは—少なくとも、西洋人の観客で超満員の状況においては—寛容、理解そして慈悲を教義の中心に置いた、明らかに宗教とは関係のないものである。
チベットが50年を超えて中国の支配を受ける中、ダライ・ラマの心を痛めているのは、チベットの人々の緊迫した寛容さと弱まっている忍耐力のようである。
先週の日曜日、ダライ・ラマが2日目の夜をメルボルンのマリオットホテルで過ごしていた頃、オーストラリアの隣国、東ティモールでは新国家誕生の祭典が開かれていた。
チベット人の人々は、消極的反抗が満足のいく自治を獲得のための唯一の方法であるとするダライ・ラマの主張に対して、これまで以上に疑問を抱き始めている。
「この問題については討議がなされています・・・それでも私は、非暴力的抵抗は正しいと信じています」と、ダライ・ラマはヘラルドに語った。・・・拳銃が簡単に手に入るとしても、それらを輸入することは不可能でしょう、と彼は言う。
「私が非暴力主義を選択するのは、ただの思考によるためだけではありません。非暴力主義は、大変実用的なものです。私たちは、チベットの長期的な将来を考えなければなりません。中国と隣り合わせに生活していかなければならないということを。中国と協力して、幸福に、平和に生きていくためには、我々が非暴力をもって自由への闘争を行うことが極めて重要なのです」
1989年のノーベル平和賞受賞者であるダライ・ラマは、現在インド北部のダラムサラを拠点としているが、長引く亡命の圧力を感じている。毎年3千人を超えるチベット人が、1959年のチベット蜂起の後、当時23歳であったチベット人のダライ・ラマと、彼を支持する約8万人の人々が通過した道を通り、ヒマラヤを越えてインドに渡る危険な旅に挑んでいる。
非衛生で社会設備の乏しい町には、精神的な悟りを求めて集まってきた西洋人の団体に難民が加わり、膨れ上がった人口は手のつけようがない。
ダライ・ラマは、亡命先の第2の祖国が環境の悪化に苦しんでいるときに、公の場で環境を思いやることについて語るのは矛盾していると告白した。しかしながら、彼は、難民となることを強制され、その延長を余儀なくされた人々の一時的な存在による意識が、環境破壊という回避できない副産物を生んだのではないと主張した。
「一度入植が決定すると・・・私たちはその場所に何世代かにわたって定住することになります。例えば、僧院がその場所に永遠にたたずむのと同じように」
仏教記念物の一つに挙げられるのは、インドでも最も貧しい州の一つであるビハール州に建てられた、3億円を超える地上152メートルの豪勢な弥勒菩薩像である。中傷者から「ディズニー仏像」の異名で呼ばれるこの仏像の建立計画により、ダライ・ラマは、彼を支持する集団から公然の非難を受けることになった。
それでも、仏像建立計画に対する支持は、私の承認を示唆するものではない、とダライ・ラマは語る。
「仏教僧として、私はもちろん仏像の建立計画を支持します。しかし、私は、そのために受ける批評について懸念していますが・・・大げさ過ぎる建築は良くないと思っています。それよりも、私たちがチベットに戻ったときに役に立つ、健康の向上に欠かせない食料・・・や健全な思考力を育てる教育に投資されるべきです。しかし、インドでの手の込んだ建築に関しては、私たちはこれらのことについて述べることができません」
ダライ・ラマは、13万5千人の亡命者達がいつか祖国に戻る日が来ることに論争の余地はないと話しているが、少なくとも彼が生存しているうちに、その日が現実のものとなることはますます難しくなっている。
公然とした中国市民軍の活動や密かな同化運動を展開するチベット占拠者には、何世紀にもわたる豊富なチベット文化や精神性を消失させることはできない、と彼は主張する。
「私たちをこの世から消すことは、そんなにたやすいことではありません。チベットがある限り、苦闘は続くでしょう。私が死ぬとき、それは挫折を意味するように取られることがあるでしょうが、それでも奮闘は続くでしょう」