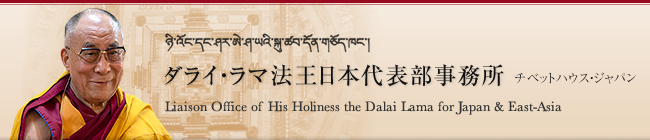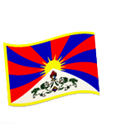毎日新聞
真夏のチベット上空で、南極や北極の「オゾンホール」のように大規模にオゾンが減り、そのメカニズムが両極とは異なることが、名古屋大太陽地球環境研究所などの調査で分かった。
原因を突き止めるため8日、同研究所などの現地調査隊が日本を出発する。昨夏に続いて2度目だが、今回は神戸大医学部皮膚科の市橋正光教授も参加し、住民への初の疫学的調査に乗り出す。オゾンが減ると地上に降り注ぐ紫外線が増え、人体への影響が心配されるからだ。「オゾン破壊による紫外線増加」という、地球全体の未来を先読みする調査にもなりそうだ。
1994年に人工衛星の観測で、チベット上空では5月〜11月ごろにかけ、オゾンが周辺より10〜20%少なくなることが分かり、中国の研究者が「オゾンバレー(オゾンの谷間)」と命名した。この減少は、日本の4〜5倍の面積のチベット高原全域に及び、冬になると回復する。年々減る傾向を指摘する学者もいるが、各国の観測施設が集中する南極と違い、これまで現地調査がなく、詳細が分かっていなかった。
同研究所は昨年8月〜10月にかけ、中国科学院大気物理研究所らと共同で、初めて地上からの観測を行った。その結果、地上約15kmの対流圏と成層圏の境目付近で、気温が氷点下80度近くまで下がっていることが判明した。
「通常なら氷点下50度ほど。驚きの新発見だ」と岩坂泰信・同研究所教授(大気物理学)は話す。標高が高く空気の薄いチベットでは、地表近くの大気が早く暖まり、夏場に猛烈な上昇気流が起きる。上昇した大気が気圧の低い上空で膨張し、気温を急激に押し下げるらしい。
こうした気流が成層圏にまで侵入してオゾン濃度を薄める対流現象に加え、人間活動で発生する硫酸系エアロゾル(空中微粒子)が吹き上げられ、オゾン破壊の元凶・極成層圏雲を生み出しているのではないかというのが岩坂教授の分析だ。上昇気流のない両極とは異なるメカニズムということになる。
今年の日中共同調査は10月まで。偏西風の強弱やエルニーニョ現象などがどう作用するかも調べる。
両極と異なりチベットでは、オゾン破壊の住民への影響が懸念される。市橋教授は地上で紫外線を測定し、住民の皮膚を診察する。「もともと高地でもあり、紫外線の影響でチベット人の皮膚は日本人より20歳ほど老化が進んでいると言われる」と市橋教授。「オゾンが20%減ると紫外線は30%増える。その影響を見たい」と話している。