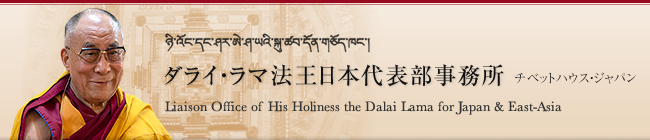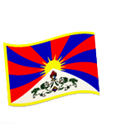(翻訳:三浦 順子)


2002年夏に来日したチベット仏教ゲルグ派の高僧で現在ダラムサラのネチュン僧院で教鞭をとっておられるゲシェー・ロサン・ケンラプ師による法話をシリーズでご紹介致します。師は、チベット仏教最高の博士号ゲシェー・ラランパを首席で卒業され、修行を積まれた南インドのデプン僧院で「学殖豊かな大僧正」に選ばれるほどの名僧でもあります。
私たちの心が外なる対象ばかりを追い求めていては、決して幸福を見出すことはできません。仏教では自らの心を変革することを求めます。この法話は、私たちの心から様々な刺激(迷妄)を断ち切って、安らぎの境地に達するための瞑想法(仏教用語で「止」、チベット語で「シネー」)を伝授するものです。
基礎段階の教え――帰依
仏教徒と非仏教徒の区別は、仏・仏法・僧伽(修行者たちの集まり)の三宝への帰依があるかどうかにかかっています。ならば、帰依とは何でしょうか。帰依の言葉を唱えようと唱えまいと、つまるところ、帰依とは心においてなす行為です。帰依を行うための因としては
- 怖れ
- 信心
の二つが必要です。人は怖れを感じるからこそ、帰依の対象に救いを求めますし、また帰依の対象に信をおくことができなければ、これまた帰依を行うことはできません。
では、人は何を怖れて帰依をするのでしょう。来世、地獄・餓鬼・畜生の三悪趣に転生する恐怖もありますし、煩悩障や所知障(一切智の境地に至るための微細な妨げと智慧の障害)への怖れもあるでしょう。こうしたものに怖れを感じて、我々は救いをもとめて帰依をするのです。この帰依の対象となるのが、仏・仏法・僧伽の三宝です。仏は帰依すべき対象を示してくれた存在であり、仏法とは帰依の対象そのもの、僧伽とはその仏法を修行する際の仲間のようなものです。
このように人は怖れを覚えて帰依するわけですが、その際、帰依の対象に百パーセント信をおかなければなりません。帰依の対象に少しでも疑いの気持ちや不信の念を抱いたなら、その段階で帰依は失われますし、帰依が失われれば、仏教徒ではありません
帰依をするにも菩提心を起こすにも、まず輪廻転生を、今の人生が終わっても、次の生に生まれ変わることを事実として受け入れることが肝心です。そして、今生の物質的幸福や世俗の喜びを得ようとしか考えない近視眼的な発想は捨てて、来世の自分に役立つことは何かを考えてみるのです。
今日は皆様にシネー(止)の瞑想法についてお話する予定です。しかしシネー(止)の瞑想法は仏教だけでなく、他の宗教にもあります。ですから仏教のシネー(止)を行じるには、まず仏・仏法・僧伽の三宝に帰依し、仏教の見解を受け入れておく必要があるのです。またこの教えを受けるにあたり、疑問が湧いたら、その疑問を私にぶつけて見てください。いや、正しい答えを知っている人がこの場にいるならば、誰が答えてもよいのです。仏教が他の宗教と異なる部分は盲目的な信仰を求めないことです。自らの知性を用いてよく吟味し、納得がいけば受け入れればよいし、納得がいかなければ受け入れなければよいのです。
盲目的な信仰は避ける
仏教では「四依四不依(しえしふえ)」、つまり四つの拠り所とすべきものと四つの拠らざるべきものを説いています。四つの拠り所とすべきもの(四依)とは、以下の四つです。
- 人に拠らず教義に拠れ
- 言葉に拠るのではなく、意味に拠れ
- その意味が完全に解明されたものに拠り、完全に解明されていないものには拠るな
- 意味が完全に解明されたものでも、智と結びついたものに拠れ
(1) の「人に拠るのではなく教義に拠れ」は、釈尊自身のアドバイスでもあり、仏教に特有のものです。あなたがたは仏教の教えが正しいものかどうかを自分の知性を用いて、吟味判断しなくてはなりません。「私が仏法を説く」などと言う人がいても、それを鵜呑みにしてはならないのです。「五根にまつわる意識(dbang shes 眼・耳・鼻・舌・身体にまつわる意識)ではなく、心の意識で判断せよ」とも言います。私たちの思考(bsam shes)は心の意識によってもたらされるものです。身体や言葉は言ってみれば心の奴隷のようなものです。心が「ここに居ろ」と命じれば身体はずっと一つの場所に留まりますし、「どこそこに行け」と命じれば、身体はそこに行きます。心が「このようなことを話せ」と命じれば、その通りに口から言葉が出るはずです。
このようにすべては心の意識(チベット語のyid shes pa=『心の意識』とは、認識し判別する心という意味で、現代語でいう『意識』とは多少意味が異なる)にかかっています。また煩悩は心の意識を縁として生じます。ですからもし煩悩を退治しようとするなら、煩悩のおおもととなっている心の意識に、この退治法を用いなければならず、それ以外に退治法を用いてもなんの効果も持ちえません。
(2) の「言葉に拠るのではなく、意味に拠れ」とは、飾られた言葉に惑わされることなく、その真の意味に拠らなくてはならないという意味です。こうしたアドバイスは実に仏教に特有のアドバイスと言えるのではないでしょうか。なぜならば、すべての判断はあなた方に委ねられているからです。イニシアチブをとるのはあなた方なのです。「わたしの言うことに、なにがなんでも従いなさい」と命令されているわけではありません。仏教の修行者というものは、心の意識を用いて考えを巡らし、判断し、それに従って行動します。さらに身体の行為よりも、心の動きが重要視されるのです。身体の行為のみでしたら、傍からもよく見え、良し悪しの分別もつきますが、心の行為、心の動きは、自分でその良し悪しを判断するしかありません。
教えは実践することが肝心
あなたがある教えについて納得したなら、実際にそれを自分に用いてみなくてはなりません。それを用いるとはすなわち瞑想をするということです。しかし一時間なにがしかの瞑想を行ない、その一時間が終わったら扉を開けて外に出て行くかのように、瞑想中のことはすっかり忘れて日常生活を送るのであってはなりません。そもそも瞑想している時間と瞑想していない時間を比べてみると、瞑想していない時間の方が長いわけです。ですから、瞑想中に得たものをそれ以外の時間に用いるのが、正しい生き方なのです。瞑想は言ってみれば、自動車にガソリンを入れるようなものです。ガソリンを入れた自動車は快適に動きますね。そのように、瞑想によって得た力で、私たちは日常生活を望ましい形で生きることができるのです。
このように仏教にまつわるものは、すべて心の行為と関連しているのです。チベット語では仏教のことをnang chos(内なるダルマ)と呼びます。「内なるダルマ」の内とは心のことです。煩悩の障害(煩悩障)、智慧の障害(所知障)をすべて浄化しつくした心には、虚空のごとき澄明さがたちのぼります。これがすなわちダルマです。
縁起
ならば、心の汚れをすべて浄化するための方便があるのでしょうか。もちろんあります。釈尊の説かれた縁起にまつわる教えがそれです。縁起とは、何かの原因に縁ってある結果が起きることを言います。
釈尊がこの世に現れるまで、さまざまな宗教では、特にヒンドゥー教などでは、この世界には全能の神や造物主がおり、この宇宙のすべてのものは造物主によって創造されたと説いていました。
しかし仏教ではそのようなことは受け入れていません。すべてのものは、原因があって生じている、これに縁ってあれが生じると釈尊は説かれたのです。さらに原因や条件にふさわしい結果が生じるものであり、ふさわしくない結果が生じることはないのです。例えば、あちらに馬がいて、こちらに赤い花があったとする。この場合、馬と赤い花は通常、因果関係にはありません。馬は赤い花を生み出すための原因とはなっていないのです。
先程も言ったように、他の宗教では全能の神や造物主が存在すると説きます。この全能の神の匙加減ひとつで、あるものは食べ物もこと欠く貧乏人となり、あるものはすべてに満たされた金持ちとなるのです。すると人は、神はあいつには幸運を恵んでやっているのに、自分にはちっとも幸運を与えてくれない、いったいどういうわけだと嫉妬するはめになるのです。しかし仏教ではさまざまな理由をあげて、造物主、全能の神の存在を否定し、すべてを引き起こしたのは自分自身なのだと説きます。ある種の宗教哲学は、人には恒常不変の霊我があり、肉体は霊我が一時まとう衣服のようなものだと主張します。こうした考えを信仰する人にとっては肉体は軽視の対象であり、爆弾をかかえて自爆することさえできるようになります。所詮、肉体などただ一時まとっている衣服にすぎず、それがだめになれば別の服をまとえばよいわけですから。チベット仏教ではすべては原因と条件によって変化すると説きます。生まれたものはすべていつか死にます。たとえば、寿命六十年の人がいたとして、その人物の残りの人生は刻々と減っていくのです。個人の存在(pudgara)もまた、恒常の存在ではなく無常であり刻々と変化しています。何故無常なる存在なのかというと、原因と条件(因縁)によってできあがったものだからです。
幸不幸となるための因はあなたの手中にある
ですから、不幸を望まないなら、不幸の因を作らないようにすればよいし、幸福を望むなら、幸福の因を作るようにすればよいのです。あなたの人生が幸福になるか不幸になるかは、全知全能の神にかかっているわけではなく、あなた自身に、幸福なり不幸なりの因を作るかどうかにかかっているのです。
煩悩障などの悟りへと至るためのさまざまな障害もまた恒常のものではなく、しかるべき退治法を用いれば退治することができます。心すらもさまざまな原因と条件(因縁)からできあがっているがゆえに、変えていくことができるのです。今あなたが体験している幸福も不幸も、おのずと湧き出てくる煩悩も、すべて前世において、あなたが身体において、言葉において、心においてなした行為の結果として生じたものであり、他の存在が作り出したものではありません。このように幸不幸はすべてあなたの手の中にあるのです。もしあなたが将来幸福を望むなら、今、身体、言葉、心を用いて善なる行為をなすべきです。それが将来のあなたの幸福の因となるのですから。
逆に今あなたに不幸が襲いかかったとしても、他人に腹を立てて、あいつのおかげで不幸になったなどと責任を押し付けてはなりません。あなたの不幸の原因は、あなた自身に、たとえば前世における悪業に起因しているのです。幸不幸いずれにせよ、過去の自分の行為の結果であると自覚することが肝心です。物質に満たされれば、自分の不幸はすべて断ち切られると考えるのは大きな誤りです。また他人があなたを幸福にあるいは不幸にすると考えるのも間違いです。なにか苦しいことにあったなら、「これは前世における自分の悪業の結果を今味わっているのだな。これで私はこうした報いを受けたので、この悪業のカルマは終わった」と考えて逆に喜ぶべきなのです。
他を傷つけない
仏教徒として肝心なのは利他の行為をなすことです。そしてもし利他の行為をなすことができなければ、せめて他を傷つけるような行為を避けるべきです。といっても自分によりよい来世が来ることを願って、他人に親切にするのは間違いです。瞑想するにしろ、俗世の仕事をするにしろ、身体・言葉・心を用いて、利他の行為ができなくても、他を傷つけることはしないようにするのです。仏教の修行は日常生活に生かさなくてはなりません。ですから、瞑想中にとどまらず、職場に出かけたときも、家庭内にいるときも、大乗仏教の修行の一環として、衆生のひとりである自分の同僚たちに、あるいは家族に、慈しみの心、あわれみの心、思いやりの心を持つことです。私たちの心のなかには確かに慈悲の心は存在します。この慈悲の心を最初に自分の身近な人間に向け、しかるのちに無数に存在する生きとし生けるものに広げていくのです。
ではなぜ、他の生きものに慈悲の心を向けなければならないのでしょうか。不幸を望まず、幸福を望むという点では、生きとし生けるもの誰もが同じです。自分が傷つけられれば苦しみ不幸を味わうように、他の生きものも傷つけられれば、苦しみ不幸を味わいます。こうしたことは、苦労して経典を読み解いたり、勉強したりしなくても、想像力を用いれば実感できると思います。
仏教は、心のさまざまな欠点、煩悩によって汚れた部分を正すための教えです。ですから、実際に修行してみて、瞑想を行ってみて、それが実際にあなたの心に役立つならば、あなたの心を良いものにできれば、確かに仏教の教えはあなたにとって有益なのです。

 学問として他の生きものに対して慈悲の心を起こさなければならないと知るだけでなく、実際にそのことについて瞑想することも肝心です。他の生きものの苦しみを自らに引き受け、その苦を味わってみることです。自分も他の生きものも苦しみを望まず、幸福を望んでいる。もし自分が他の生きものに危害を加えたならば、相手は苦しむ。そのようなことはあってはならないと心底感じることで、煩悩を断ち切ることができるのです。
学問として他の生きものに対して慈悲の心を起こさなければならないと知るだけでなく、実際にそのことについて瞑想することも肝心です。他の生きものの苦しみを自らに引き受け、その苦を味わってみることです。自分も他の生きものも苦しみを望まず、幸福を望んでいる。もし自分が他の生きものに危害を加えたならば、相手は苦しむ。そのようなことはあってはならないと心底感じることで、煩悩を断ち切ることができるのです。
本尊のヨーガなどの瞑想によって、心の平静さを得ることはできるでしょう。しかしそれによって心の平静さを得るだけでは充分ではないのです。真の心の平静さを得るには、自らの心の欠点を知り、それにふさわしい対処法を施していくことも大切なのです。
私たちは他の存在を味方・敵・無関心な相手の三つに分別します。このような分別を行うのも自分自身へのとてつもない執着心があり、なんとしても自分を守りたいと思っているからです。自分の味方である存在は慈しみ、自分の敵である存在には怒りをおぼえる。さらに愛着も怒りも覚えない無関心な相手というものがいる。怒り・貪り・無知の三煩悩はこれらのものが基盤となって生じるのです。
ですから他者を味方・敵・無関心な相手の三つに分別してはいけません。そもそもそう分別する理由さえないのです。敵も味方も真髄を欠いています。今あなたが敵だと思いこんでいた相手が、将来味方に変じたり、味方だと思っていた相手が敵に変じたりすることもあるわけですから。また今、大したことのない相手だと思っていた存在が、将来あなたにとって、とても有益な相手になることもあります。こうした事実はわざわざ経典にあたる必要もありません。そのことについて思い巡らしてみれば、そうとわかるはずです。一時たりとも離れ離れになっているに忍びない愛しい相手が、いつしかその名前を聞くだけでもむかつくような相手になっている。反対に、最初はなんて嫌な相手だろうと嫌悪していた相手が、いつのまにか限りなく愛しい相手になっている・・・。
私は別に敵も味方も存在しないと言っているわけではありません。敵も味方も存在します。ただ、敵であるから憎む、味方であるから愛するという態度を捨てて、どうしてあるものが敵と感じられ、あるものが味方と感じられるのか、その理由を理解し、敵味方を分別するような態度を捨てなさいと言っているのです。
ではここで、瞑想してみてください。敵なるものも味方なるものも真髄を欠いていること、自分も他の生きものも、幸福を望み、不幸を避けたいと願っている点では同じであることをしばらく瞑想してみてください。
瞑想の際の心構え
瞑想する際には、大日如来の七つの姿勢をとるとよいでしょう。大日如来の七つの姿勢とは
- 結跏趺坐(けっかふざ)
完全な結跏趺坐ができないならば半跏坐でもよいです。その場合右足を前に出すのがよいでしょう。 - 半眼で視線は鼻先に
目はあまり遠くを見るのではなく、なんとなく鼻先を見ている形で。また、仏像などをじっと見つめて瞑想する人もいますが、「シネー(止、心の平静さ)」の瞑想は目などの五官にともなう意識ではなく、心の意識において行うものですから、目の意識を働かせても役に立ちません。人によっては目をつぶったほうが、「シネー(止)」をよく達成できると主張する人もいるでしょう。それはそれでけっこうです。 - 背骨はまっすぐ、からだが前後左右に傾ぐことなく、背筋をのばして。
- 肩は水平に保ち後ろに引く
- 舌先は上口蓋に、また歯を噛みしめることなく、リラックスして。
- 頭は左右前後に傾ぐことなくまっすぐに保つ
- 手で禅定印(ぜんじょういん)を結ぶ
さらに呼吸を荒げることも、浅すぎたりすることもなく、くつろいでください。
なぜ瞑想する際に、このような姿勢をとるべきなのかというと、体が正されれば体の中に走っている脈管が正され、脈管が正されれば脈管のなかを走る風が正され、風が正されれば心が正されるからです。密教では、風は心の乗り物といいます。風の行くところどこにも心は行くのです。風は目の見えない存在、心は、目は見えるものの脚のない存在に喩えられます。片方だけでは動きはとれないが、両者が一体となることで、自由に動けるようになるのです。
瞑想にふさわしい姿勢がとれたところで、先ほど私が述べた瞑想をしてみてください。
瞑想には2種類あります。分析的瞑想(dpyad sgom)と心を平静に一点に集中させる瞑想です。あることがらについて分析しながら瞑想するのが分析的瞑想です。自分が敵とみなしている相手が本質的に敵そのものなのかどうか、味方とみなしている相手が本質的に味方なのかどうかを瞑想するのも、分析的瞑想の一種です。分析的瞑想とは理由を問う瞑想法です。これを充分にやってからでなければ、次の段階の瞑想に進むことはできませんし、後になって、ああではないか、こうではないかと心に疑いが生じることでしょう。
分析的瞑想を行ない、自他ともに苦を望まず、幸福を望んでいるがゆえに、他の生きものに苦しみを与えまい、敵、味方と区別するのは意味がないから、他の生きものに危害を加えるようなことはしまいという結論に達してみてください。
質疑応答
Q :世界には憎悪や憎しみが渦巻いています。我々はそれにどう対処すればよいのでしょうか。
ゲシェー:
まず自分の心の中を覗き込み、自らのなかに怒りや憎しみがあることを知り、それを退治するべく努めてください。自分の中の怒りを滅することで、次第に外の世界にある怒りを滅していくことも可能になります。
外の世界の怒りを、他者の怒りを消すのはとても難しいのです。それより自分の中の怒りを滅し、自分の心をコントロールするすべを覚えたほうがよいでしょう。裸足で岩道を歩けば、足の裏は傷つきます。その時、ごつごつした地面に腹を立てても無意味です。代わりに分厚い靴を履けば、足の裏は傷つかずに済みます。怒りが生じたなら、怒りの対処法である忍耐(忍耐とは苦をただ忍ぶことではなく、いかなることが生じようとも揺るがない心を育むこと)を行じてみてください。腹の立たない時にいくら忍耐心を行じても、いざ腹が立つような状況が生じたときに怒ってしまってはなんの役にも立ちません。腹の立つような状況でこそ、怒りの生じた時こそ、忍耐心を行じるべきなのです。なぜならば忍耐は怒りの対処法だからです。
ダライ・ラマ法王もおっしゃっています。腹立たしい相手を敵と見なすかわりに、自分の忍耐行の師であると、「忍耐心を養いなさい」とアドバイスを与えてくれる先生であると思いなさいと。このように忍耐の心を養うことで怒りは鎮めることができます。
皆さんのような社会人は、部屋の中に独り篭って瞑想の時間を持つのも大変でしょう。日々の仕事があるわけですから。そのかわり、日常生活の中で、仕事に行くにも、車に乗るにも、歩いて行くときにも、常に自分の心のありようを観察し、自らの心を訓練していってみてください。そうすれば、日常生活のなかで仏教の教えを実践していることになります。
仏の境地に達するということはもしかして非常に簡単なことなのかもしれません。身体・言葉・心を存在の真のありように適した形で動かすことができれば、それがすなわち仏の境地なのですから。ですから、あえて部屋に篭って瞑想しなくても、日常生活の中で正しい形で身体・言葉・心をコントロールするすべを習得できればよいのです。
Q :人ごみの中にいると、それだけでもやりきれない思いに、嫌悪感にかられます。どうすればよいのでしょうか。
ゲシェー:
そうした嫌悪感が生じるのも、過去に何かの原因があり、その結果が現在あなたの身に生じているからです。あなたは自分の身に起きたことの原因を外に求めてはいけません。もともと自分の中に原因があり、その結果を自分が引き受けているにすぎないと思ってください。ただし嫌悪の情というものは、怒りそのものではないので、どうしても退治すべき煩悩ではないのです。ただしその嫌悪の情に怒りや貪りといった根本煩悩が混じっているならば、やはり忍耐の心を行じるべきでしょう。貪りの心を退治するには、不快なもの、不浄なものを観想します。また先ほど述べたように、敵味方の分別をする必要がないことを、平等心を瞑想するのも良いでしょう。あるいは縁起について考えてみることもよいでしょう。
Q :肉体と心の関係を教えてください。
ゲシェー:
人を肉体と心に切り離して考え、肉体は衣服のようなものであり、死ぬのは衣服を脱ぎ捨てるのとなんら変わりないと考える宗教もあります。そういう宗教は肉体や肉体に基づく苦しみを無視しがちです。しかし仏教では、人(個人存在gang zag)は肉体の上に成り立っているとみなします。歩くといった単純な行為も肉体があって成り立つものです。仏教では、五蘊(人間存在を身心の五つの要素に分けたもの)に拠らない人(個人存在)はありえないとみなしています。しかし宗教によっては、肉体と心は別のものであり、肉体を軽んじて、切り捨ててもいい、自殺してもなんらかまわないと教えるものもあるのです。仏教では肉体と心を関連付けて考えます。
Q :縁起論を誤解して、他人が不幸な目にあうのはその人自身の過去生に原因があり、不幸な境遇に陥った相手になんら同情する必要はないと主張する人もいますが、そういう人々の考えをどう正したらよいのでしょうか。
ゲシェー:
苦しんでいる他者に対して、「おまえが苦しんでいるのは前世で悪いことをした結果だ。因果応報だ」と言って哀れみの心を起こさずにいるのでしたら、大乗仏教の道そのものを、いや仏教徒としての道そのものを踏み外しています。苦しんでいる相手に哀れみの心を起こすのは当然です。「この人は因果の法則を理解せずにこんな目にあってしまったんだ。なんて可哀想に」と思わなければならないのです。
仏教徒ならば、前世を、輪廻転生を百パーセント受け入れています。そして輪廻には始まりはないのです。輪廻に始まりがないなら、生きとし生けるものすべてが、最低一度は我々の父や母であったことがあるはずです。かつて自分の両親であった貴い存在が目の前で苦しんでいるのにどうして哀れみの心を起こせないことがありえましょうか。
逆に自分がなにかの苦しみにあっても、その苦しみの原因を外の世界に求めてはなりません。
チベットを例にとってみましょう。チベットは他国を侵略するための武器もなければ、そのような意図もありませんでした。チベットは豊かな国ではなく、食糧もかつかつです。そんな国でチベット人は自分たちのささやかな幸福な生活を営んでいたのです。にもかかわらずあれほどの苦しみを受けた。その原因は過去のカルマとしかいいようがありません。チベットが中国に侵略を受けてからすでに50年あまりの歳月が過ぎました。しかしダライ・ラマ法王は常々、中国人に対して怒りの心を持ってはいけない、逆に彼らが悪業をなしたことに憐れみの心を持ちなさいとおっしゃっています。
輪廻が存在する証拠は様々なところで見て取ることができます。どんな生きものも本能的に自分の仔を慈しむことを知っています。こうした本能も前世があるからこそ生じるのです。同じ親から生まれた兄弟の性格や知性が異なるのも前世からの影響といえます。
Q :私は瞑想の初心者ですが、毎朝、瞑想するとして、どのような瞑想を行うべきでしょうか。
ゲシェー:
先ほど行ったような瞑想でもよいですし、自分の心に怒り・貪り・無知の三煩悩のうち、どれが一番強いか見極め、その煩悩を特に退治するための瞑想法を行ってみてもよいでしょう。
Q :人が事故や災害やテロにあって死ぬというのはその人の前世に原因があるのでしょうか。
ゲシェー:
そうです。というより、原因のない結果はありえません。然るべき原因を積むことで、何かの結果が生じるのです。外の世界を見てもそのことは明らかでしょう。種が無ければ花も咲かず、木も生えません。ですから、私たちがいかなる苦難を受けようと、究極的にはその原因は自分にあります。他人にその原因を押し付けることはできません。
Q :では、そうした不幸にあった人々のために祈ることは、何か役に立つのでしょうか。
ゲシェー:
まったく役に立たないとは言いませんが、単に祈るだけで救いがもたらされるなら、我々はとっくの昔に輪廻から脱出できているはずです。釈尊は我々を救うために悟りを開かれ、我々に無量の慈悲の心を注いで、我々をなんとか仏の境地に導こうとしています。しかし我々の身体・言葉・心が不浄であるために、いかんともしがたく、そこで我々はいまだに輪廻世界に留まっているのです。でも死者のために祈願することは、死者のために道をつけてあげることであり、それはそれで大切な役目があると思います。また祈願したあなた自身、善根を積むことができます。

最初に「シネー」(寂止)とは何なのか、簡単にご紹介したいと思います。それから「シネー」の各項目についてお話しましょう。その際、釈尊自身の教えのみならず、釈尊の教えに解説を加えたナーガールジュナ(龍樹)などの大学者たちが著した論書にも基づき、「シネー」を解説したいと思います。論書を著した大学者たちには、ナーガールジュナのほかに、シャーンティデーヴァ、アサンガ、カマラシーラといった方々がいらっしゃいます。
それではまず、「シネー」とは何か、「シネー」を行じるにあたって、どのような準備が必要かをお話しましょう。
五つの障害
「シネー」を行じる際に、断ち切るべき障害となるものが五つあります。
- 「懈怠(けだい)」(怠慢になること)
- 「失念」(瞑想の対象を失うこと)
- 「昏沈(こんちん)」「(心が沈み込み散漫になること)と「掉挙(じょうこ)」(心が昂ぶること)
- 心が「昏沈」「掉挙」していることを知りながら、しかるべき対処法をとらない
- 逆に必要もないのに対処法をとり続ける
これら五つの障害を断じるために、八種類の行を行います。
「懈怠」、つまり怠慢にもいろいろあります。瞑想を始めないうちから、「瞑想なんかしたくないなあ」といった気持ちが起きる。こうした形の怠慢は「努力」によって退治することができます。「努力」を起こすには、「シネー」を達成したいという願望が必要です。そのような願望を起こすには、そのおおもとに信仰がなければなりません。また努力の結果、「軽安(きょうあん)」が得られます。「軽安」とは、難なく望みどおり瞑想状態に入れる心の巧みさ、しなやかさのことです。「懈怠」への対処法には、「信仰」、「願望」、「努力」、「軽安」の四つがあるわけです。
「失念」(瞑想の対象を失うような場合)には、「念」(注意深さ)が求められます。
心が沈み込んだり散ったりする「昏沈(こんちん)」に陥った際に役立つのが、「正知shes bzhin(しょうち)」です。「正知」とは、瞑想中に心が沈み込んだり散ったりする時に、すぐさまそれを察する力のことです。正知そのものは、心が沈み込んだり散ったりしたその状態から解き放ってくれはしません。心がこういう状態になったから、しかるべき対処法を施さなくてはなりませんよと警告を発する役目なのです。心が沈み込んだり散ったりすると、集中できなくなるために対象を逸してしまいます。そこでしかるべき対処法をとり、いずれにも偏らない金剛のごとき平等心に落ち着くのです。
以上が「シネー」を行じる際の基礎となる教えです。
「シネー」を行じる際に、要となるのは二つです。ひとつは意識を一点に集中でき、瞑想の対象を失わないこと。もうひとつは、瞑想の対象が明るく澄みわたっていること。「安定」と「明瞭さ」の二つです。これぞ「シネー」の本質です。
「昏沈(こんちん)」 ― 沈み込んだ心 ―
明るく澄みわたっているはずの瞑想の対象がぼけてきたならば、心が沈みこんできた証拠です。心がさらに沈み込んだならば、眠くなってきます。「沈み込んだ心」にも、粗いものと微細なものの二種類があります。昂ぶった心である「掉挙」にも同じく粗いものと微細なものがあります。
まず、「昏沈(心が沈みこむ)」の本質とは何かというと、心が対象を捕らえる力が弱まって、対象の鮮明さが失われることです。そのことについてカマラシーラは『修習次第?』で、「暗闇にいる人のように、目を閉じたように、心が対象を明瞭に見られないときを沈み込んでいると理解すべきである」と述べています。カマラシーラの『修習次第』ほど、「昏沈」について詳しい説明はありません。
では、「粗い沈み込んだ心(bying ba rags pa)」とは何でしょうか。心が対象に定まりながら、それが明瞭でなくなった状態を指します。「微細な沈み込んだ心(bying ba phra mo)」とは、心が対象から揺らぐことなく対象そのものも明瞭でありながら、少々対象の把握力が緩んできた状態を指します。手に紐を握った人を想像してみてください。ある人は目覚めていて紐をしっかり握っている。別の人は居眠りしかけているが、一応紐を握っていることは握っている。後者の状態が、「微細な沈み込んだ心」です。
心が沈み込み、それを察知したならば、それを取り除くべく、しかるべき対処法をとらなくてはなりません。たとえば、仏の姿や無常という概念を観想するなどの瞑想を行い、心が軽くなり明晰になったなら、再び「シネー」に戻ります。
人によっては、瞑想しているつもりで、心が沈みこんだ状態のままの人もいます。このような人たちの意識は明晰ではなく、暗く垂れ込めています。沈み込んだ状態を「シネー」と取り違えてそのまま瞑想を続けた人は、来世、知性のぼんやりした人になる恐れもあります。
「掉挙(じょうこ)」 ― 昂ぶった心 ―
「掉挙」とは、心が対象に定まらず、対象以外に散乱している「昂ぶった心」のことを言います。その本質は、貪りの心によって意識が様々な対象を追いかけてしまうことにあります。「昂ぶった心」にも、「沈み込んだ心」と同様、粗いものと微細なものの二つがあります。意識が瞑想対象から完全にずれてしまうのが、「粗い昂ぶった心」です。瞑想対象から完全にずれなくても、意識が対象からぶれたり揺れたりするのが――たとえば氷そのものは溶けていなくても、そのまわりに水が滲み出て来るような――「微細な昂ぶった心」です。
「沈み込んだ心」と「昂ぶった心」については、経論ともに多くの解説がなされていますが、以上をもって肝心要の部分は解説できたと思います。
「シネー」に至る心の九段階
1)それぞれのものに心を安住させる
私たちの心は常に外界の様々なものに魅せられ、心が揺れ動いています。外界の対象に揺れ動く心を収斂させ、対象に意識を集中させます。これが第一段階です。瞑想の対象は仏の姿でもなんでもかまいません。それに意識を集中させるのです。
2)続けて安住させる
こうやって瞑想しても、私たちの意識はいつも揺らいでいます。対象に固定した心が揺らがないよう、あるいは心が沈み込んだり昂ぶったりしないよう注意して、続けて安定させます。
瞑想の対象については、いろいろあるでしょう。無常、空性など様々なことを瞑想の対象にすることができます。
3)引き戻して安住させる
ここで心が沈み込んだり昂ぶったりして、瞑想の対象を逸してしまっても、再び心を対象に引き戻します。これが第三段階です。
4)身近に安住させる
心が散乱したことを知って、それを断ち切り、ひとつの対象に努力して安定させます。
5)折伏する
「三昧(さんまい)」(精神を集中し、雑念を捨て去ること)の「シネー」の徳性を知り、それに対して喜びの心を持ちます。これを「折伏する」と言います。
6)鎮める
心が散乱することを過失とみなして、「三昧」を喜ばない心を鎮めます。
7)極めてよく鎮める
貪欲の心や不満足感、心が重く沈み込んで怠慢になることの過失を知り、それが生じたところで鎮めます。
8)集中する
この段階では、心が沈み込んだり昂ぶったりといった過失は完全になくなっています。では、この状態が「シネー」かと問われれば、違います。ここでは果断なく努力して、続けて「三昧」の状態に安住します。
9)平等なる境地に安住させる
このあとに、最後の段階である「平等なる境地に安住させる」が来ます。この段階でも「シネー」は達成されていません。しかしこの境地に至れば、修行者は自分が望むだけ、努力せずに、瞑想を行うことができます。
「軽安(きょうあん)」
では「シネー」そのものはどうすれば到達できるのでしょうか。これには身体の「軽安(きょうあん)」と心の「軽安」の二つが必要です。「軽安」とは、なんの努力もしなくても、易々と瞑想が達成できてしまう軽やかさ、しなやかさ、巧みさのことをいいます。瞑想する際の様々な不快感、やりにくさ、障害、煩悩をすべて断ち切った状態のことです。順序からいうと、まず「心の軽安」、次に「身体の軽安」を得ます。
「心の軽安」とは、何を瞑想しても易々とそれが達成でき、いくらでもその境地にとどまれる心のしなやかさのことです。「心の軽安」を獲得できれば、その力によって身体の感覚が変わり、「身体の軽安」を獲得することができるのです。そして「身体の軽安」が得られれば、身体の中に安楽が生じ、それによって心の中に安楽が生じます。以上述べた要素がすべて兼ね備わったところで、「シネー」の境地に至るのです。これは簡単に得られるものではありません。瞑想をちょっと試みれば、たちまち「シネー」の境地に至れるなどということは決してありません。いかなるものを瞑想の対象としようと、これまで述べた必要な要素をすべて兼ね備えることができるよう、ひたすら努力を続けることが肝心なのです。一生涯かけてもまだ達成できないなら、生まれ変わってもまだ続ける。その程度の覚悟が必要です。手っ取り早くやろうなどと甘い考えを抱いて瞑想しても、途中で放棄するのがおちです。
六つの力
「シネー」(寂止)の各段階を達成するにあたり、六つの力が必要となります。『声聞地』に述べられているに六つの力とは以下のものです。
- 聴聞力(thos pa’i stobs )
- 思惟力(bsam pa’i stobs)
- 憶念力(dran pa’i stobs)
- 正知力(shes bzhin gyi stobs)
- 精進力(brtson ‘grus kyi stobs)
- 習熟力(‘dris pa’i stobs)
- 聴聞力
聴聞力により、「シネー」の九段階の最初のもの、「それぞれのものに心を安住させる」が達成できます。初心者は、師からのアドバイスに耳を傾けて、対象に心を安定させます。 - 思惟力
思惟力によって、「シネー」の九段階の二番目「続けて安住させる」が達成できます。まず、教えを受けて、言われたとおり対象に心を集中させることを行い、さらに、自分自身でも考えをめぐらして対象に心を集中させ、安住させるとはこういうことなのかと納得する。それによって、心を対象に続けて安住させることができるようになるのです。 - 憶念力
憶念力(注意深さ)によって、「シネー」の九段階の三番目と四番目「引き戻して安住させる」「身近に安住させる」が達成できます。対象から意識が散乱しても、注意深さによって、それを押しとどめることができるからです。 - 正知力
正知力によって、「シネー」の九段階の五番目と六番目「折伏する」と「鎮める」が達成できます。 - 精進力
精進力によって、「シネー」の九段階の七番目と八番目「極めてよく鎮める」「集中する」が達成できます。 - 習熟力
習熟力によって「シネー」の九段階の最終段階「平等なる境地に安住させる」が達成できます。
この六つの力ですが、習熟力を生むためには、まず精進力がなければなりません。精進力を生むためには、正知力がなければなりません。正知力を生むためには、憶念力がなければなりません。正知力とは、「シネー」を行じている最中に、沈み込みや昂ぶりが現れていないかを監視する力のことです。ですから、そもそも憶念力(注意深さ)そのものを欠いていては、正知力も生まれようがないのです。さらに憶念力を生むには、思惟力がなければなりません。思惟力を生むには、まず聴聞力がなければなりません。このように六つの力は、最初の力が次の力を生み出し、次の力がさらにその次の力を生み出していくのです。
これまでは、「シネー」(寂止)についての簡単なご紹介です。紹介されたものを、実際に利用してみるかどうかは、あなたがたの自由です。
ここまで私がお話した教えは、なにも私自身が勝手に作りだした教えではありません。釈尊の説かれた教え、それに対するインドの学者たちの解説書、チベットの学者たちの解説書などに基づいてお話しているのです。『ラムリム』の教えには、インドの大学者たちの教えが凝縮されたかたちで入っています。
「シネー」(寂止)を行じる際、沈み込みや昂ぶりがどういう状態であるかを知ることが大切です。心が昂ぶるとはどういうことかというと、心が何か魅力的なものに惹き付けられてしまうことです。つまり煩悩のなかの貪りの心と関係があるのです。
瞑想をしている際、心が対象から逸れるのはよくあることです。昂ぶり(掉挙)だけが、瞑想の対象を失わせる原因ではありません。瞑想中に何か別の思考が生じれば、それだけで瞑想の対象を失ってしまいます。しかし、三大煩悩である怒り・貪り・無知のなかで、一番心をかき乱すのは貪りなのです。怒りは確かに破壊的な威力を発揮しますが、四六時中怒ってばかりいることはできません。怒りによって、瞑想の対象を失うこともないわけではありませんが、少ないといえます。
そのことは、みなさんが自分自身を振り返ってみてもわかるはずです。朝起きてから夜寝るまで、仕事をしていても、家事をしていても、気懸かりなのは物質的な事柄や、金にまつわることばかり。怒るとしても時々にしかすぎません。このように、日常生活で私たちの心を揺るがすのは、貪りにかかわることが多いのです。まあ、怒り狂って、車を暴走させる人もいるようですが(笑)。
石や樹などといったあまり魅力的でないものを瞑想の対象とすべきではないと言う人もいます。瞑想の対象には仏の姿とか、無常・空性などが良いのです。そうすれば、煩悩を退治する力ともなってくれるはずです。
無常
釈尊も、サールナートで初めて仏法を説いたとき(初転法輪)、まず無常の教えを説かれました。そして、クシナガラで入滅の際に、最後に説かれたのもやはり無常の教えでした。無常の教えは、仏教の入り口のようなものです。修行に精進することができるのも、無常の教えがあるからです。最終的に仏の境地に至ることができるのも、無常の教えがあってこそです。
無常もいろいろな姿をとります。外の物資的世界を観察してみても、そのことはわかるはずです。髪の毛を剃っても、また生えてきます。内部で微細な変化が生じ、その変化が最終的に外面的な粗い変化となって現れる。つまり黒い髪なり、白い髪なりが生えてくるわけです。内からの変化がなければ、外に変化が現れることはありません。
年をとると、身体を構成していた地水火風の四大の力が弱まり、さまざまな老いの兆候が現れます。例えば私でしたら、もうすでに歯がぐらついています。こうした老いの変化は私たちすべてに襲いかかる運命なのです。無常の理についてどうして考えを巡らす必要があるのかというと、私たちがいつ死ぬかわからないという現実に、無常が結びついているからです。人として生まれたならば、100パーセント死ぬ運命にあります。ひょっとしてここにいる私たちだって、明日には死んでいるかもしれません、大地震でも起きるかもしれませんし。
にもかかわらず、私たちは自分が死ぬことがないように振舞って生きています。明日は死ぬまい、明後日は死ぬまい、今日生きている人は明日も明後日も無事だろう、すべては恒常のままであるふりをして生活を送っています。この私自身も、この前インドから来て今日は日本におり、明日はインドに戻って・・・などと計画を立て、無常についてあえて考えようとしません。こういうのを常見へのとらわれといいます。私たちは皆、内心、昨日の自分がそのまま今日ある、今日の自分はそのまま明日あると思い、自分が変化していることにはあえて目をつぶったままです。
無常のなかでも、時に自分がいつ死ぬかわからないことについて瞑想してみることが大切です。米国でこれと同じ話をしたら、そんな不吉な話は聞きたくないといわれました。しかし、これこそが仏教の一番大切な教えなのです。ちなみに米国で貪りの退治法として、身体を不浄なものとして瞑想する方法を教えましたら、これまた嫌がられました。でも、私は皆さんに、力及ばずながら、仏教の教えをそのままお伝えしたいと思っています。
無常に関連して大切なのは、人はいつ死ぬかわからないという厳然たる事実です。しかし、人はいつ死ぬがわからないといっても、世俗の出来事を今すぐ放棄せよといっているわけではありません。死がいつ訪れるかわからないことを考え、貪りの心をなるべく少なくしなさいといっているのです。死ぬときには、この肉体は後に残していくしかありません。今生でいくら苦労して物質的な富を築いても、死ぬときはそれを残していくしかないのです。では、無常について、あるいは人はいつ死ぬかわからないということについて、ここで五分ほど瞑想してみましょう。
(参加者全員で五分間、瞑想の実践)
質問者Q :「シネー」(寂止)と観を行じることでどのようなご利益があるのでしょうか。
ゲシェー・ロサン・ケンラプ:
観(lhak thong)とはlkak par thong pa、直訳すれば「特別に観じる」です。心を安住させて、ものごとの究極の本質を、つまり空性を智慧によって観察することをいいます。
「シネー」(寂止)を行じて、どのようなご利益があるかというと――すなわち、これらを行じて、どのような修行の成果を得られるかというと、心を善なる方向のみに向けることができるようになります(不善の方向に向けるのでしたら、修行なしでも誰でもできるわけですから)。
如所有性(にょしょうしょう あるがままなること、法性)と盡所有性(じんしょうしょう すべての現象界の差別のありさま)を智慧によって観じるのが、すなわち観です。声聞・独覚・大乗の三乗すべての果は、止観によってえられるともいえるのです。
「シネー」(寂止)を完成するには、さきほど述べた九段階の各段階に習熟しなければなりません。心を一点に集中させるすべがわかっていなければなりません。
知恵にもさまざまな知恵があります。知恵イコール「善」ともいえないのです。慈悲なき知恵、人類を滅亡させるような武器を発明する知恵もあります。そうした知恵は、仏の方便に反する知恵です。他を害するための慈悲なき知恵です。本当の知恵とは利他の心にあり、他人を慈しむのが善なる知恵、本当の智慧です。
すべての心のありようは、善なる智慧は、止観の中に集約することができるともいわれます。とはいっても、すべてが止かといわれれば、そんなことはありませんし、すべてが観かといわれれば、それもまた違います。