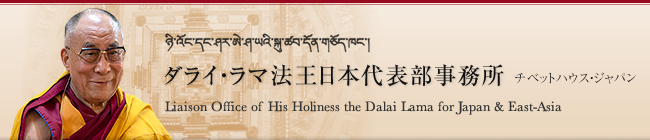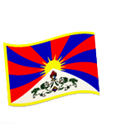チベット亡命政権 情報・国際関係省著「チベット入門」より抜粋
1642年、ダライ・ラマ5世はモンゴルの首長グシリ・ハーンの後押しを受け、それまで分裂していたチベットをまとめ、聖俗両界の最高権力者となった。それ以来、チベット人はダライ・ラマ5世を「ゴンサ・チェンポ(最高の統治者)」と呼び、法王の威信ははるか国境を越えて広がった。
ダライ・ラマ5世は、モンゴルとの関係を保ったばかりでなく、清の皇帝たちともつながりを深めた。ダライ・ラマ5世にまだ政治権力がなく、また、漢族が中国を制圧して清朝を興す以前の1639年、ダライ・ラマ5世は、満州の太宗ホンタイジからその都ムクデン(現・瀋陽)に招待された。ダライ・ラマ自身は行くことができずに代理を派遣したところ、代理はホンタイジ皇帝から大変丁重なもてなしを受けた。こうして、ダライ・ラマと清朝皇帝との間にチュ・ユン関係が開かれることになった。
モンゴル諸帝との場合もそうだったが、チベット僧と清朝諸帝の間に中国が介在することはなかった。オーウェン・ラティモアが記しているように、
| 存在したのは清帝国であり、中国は帝国の1部にすぎない |
のである。
中国が清に併合された後の1653年、順治帝は、ダライ・ラマ5世を首都北京へと公式招待した。その歓迎ぶりはかつて例をみないものであり、チベットの王であり同時に中央アジア仏教界きっての指導者ダライ・ラマ5世を、みずから4日もかけて北京郊外に出迎えた。この訪問について、米国の中国学者でもあり外交官の経験もあるロックヒルは、次のように記している。
| (ダライ・ラマには)主権国家の代表とまったく同等の儀礼が尽くされ、清側の態度を見る限り、国家代表と見なしていたとしか思われない。この時期、ダライ・ラマ5世の政治権力はグシリ・ハーンの軍事力と全モンゴル人の信仰心とに支えられ、順治帝に異議の差しはさむ余地はなかった |
ダライ・ラマ5世と順治帝は、このとき前例のない高い称号を互いに与えあい、チュ・ユンの関係が確認された。白書は、順治帝がダライ・ラマに与えた称号のことにしか触れておらず、ダライ・ラマが同じように順治帝に与えた称号については都合よく省いている。中国の見解では、ダライ・ラマは順治帝のこの行為によって、チベットを統治する法的根拠を得たと考える。しかしそれは、両者が称号を交換した行為の本質を意図的に欠落させる解釈である。かりにダライ・ラマの政治権威が清から与えられた称号に由来すると考えるのなら、同様に、順治帝の権威もダライ・ラマの与えた称号に由来することになる。
清代(1644〜1911)を通して、チベットと諸帝の関係は正式にチュ・ユンの関係に基づいていた。皇帝[康熙(こうき)帝]が派兵の要請を快諾し、チベットに侵入したモンゴルのジュンガル軍を追い出して、1720年、新生ダライ・ラマ7世をラサに送り届けたこともあった。
清はこれ以外にも、18世紀だけでチベットに3度軍隊を送っている。1回はネパール・ゴルカ軍の侵入を阻止するためのもの(1792)で、あとの2回は内戦後の秩序を回復させるためのもの(1728と1751)だった。いずれもチベットの要請に応えた派兵であり、チュ・ユンの関係に訴えた行動といえるだろう。
チベットが内乱に乱れていたこの時期、清はチベット支配をある程度成功させている。しかし、清の支配力はその後急速に減退し、チベットがカシミールからの侵入(1841〜1842)、続いてネパールからの侵入(1855〜1856)、さらに英領インドからの侵入(1903〜1904)によって紛争に巻き込まれると、清は完全に出番を失った。さらに19世紀の半ばには、清の諸帝{と駐蔵代表(アンバン)}の役割は形骸化するに至るのである。
話は前後するが、白書がことのほか注意を払っているのは、1793年に乾隆(けんりゅう)帝が制定した、いわゆるチベットに関する29条の布告と、駐蔵代表の任命に関する部分である。白書に登場する「布告」は勅命のごとくに描写され、まるで清の支配がチベットに広く行きわたっていたかのように読める。しかしこれら29条はあくまで乾隆帝の提案集であり、対ネパール紛争の事後処理としての、チベット政府の改革案だった。他方、アンバンというのは、植民地総督でも行政宮でもなく、基本的には大使であり、清の国益保護とダライ・ラマ保護のために派遣されていた。
ネパールとの間にちょっとしたいさかいがあった後、1792年にネパール・ゴルカ朝がチベットに侵入した。乾隆帝はダライ・ラマの求めに応じて大軍を派遣し、ゴルカ軍を討ってチベット−ネパール間に平和条約を調停した。チベット政府による派兵要請は清にとってこれが4度目であり、清としては、チベットがふたたぴ紛争に巻き込まれて清の軍隊がこれ以上出動要請を受けることがないよう、チベットの内政に何らかの発言権を確保しておきたいと考えた。
乾隆帝の「布告」は、皇帝の保護者としての立場から出た提案であり、臣民統治をめざした命令ではない。皇帝の使節としてダライ・ラマ8世に派遣され、同時に清軍の司令官でもあった福康安(ふくこうあん)将軍は、それを裏付けるように次のごとく述ペている。
| 皇帝は臣(わたし)にあれこれ細かい指示をなさり、たいへん時間をかけて、あらゆる問題についてひとつひとつ論じられました。チベットに平和が訪れ、永遠に繁栄が続くことを、皇帝が望んでおられた証拠です。ダライ・ラマが皇帝に謝意を表して提案を受諾するのは間違いないでしょう。提案はすでに1度議論されており、内々に同意を得ているのです。 しかしもし、チベット人がどうしても旧態然とした習慣を捨てられないというのであれば、皇帝は軍隊を引き上げ、アンバンと駐屯軍を撤収なさるでしょう。そうして、今後同じような事件がおきても、皇帝は関知なさらないことでしょう。ですからチベット人は、自分たちの好き嫌いや事態の軽重を考え、みずから判断を下せばいいのです。 |
チベット人は、皇帝の提案を採るか捨てるかという二者択一は行わず、29の項目から自分たちの益になるものを採り、そぐわないものを捨てた。先々代のパンチェン・ラマ、パンチェン・チューキ・ニマ[=パンチェン・ラマ9世]もこう言っている。
| 清の政策がチベット人の考えに一致すれば、アンバンの提案は受け入れるつもりでした。逆に、(中略)提案が少しでも国益に反するものであれば、皇帝はチベットにおける無力さを知ることになったでしょう |
「29条の布告」のなかでひとつ重要なのは、ダライ・ラマやパンチェン・ラマをはじめとする転生者を、金壷に入れたクジを引くことによって決定する[=金瓶掣籤(きんぺいせいせん)]いう提案だった。しかしこの大切な選出儀礼は、引きつづきチベット政府と高僧たちの監督下におかれ、儀式はあくまでもそれまでの伝統的な宗教作法に則(のっと)って行われた。こうして、金壺を使った最初の儀式となるべき1808年のダライ・ラマ9世の選出のときにも、チベット人は旧来の方法に従ったのである。
この「布告」でもうひとつ重要なのは、アンバンの役割だった。アンバンは、ときに大使のようであり、ときに旧来の植民地総督のようでもあった。このアンバンの役割については、アンバンのユタイがインド外務大臣モーティマー・デュランドに行った1903年の説明がもっとも的確なので、大臣の報告から少し引用しよう。
| アンバンはラサの客人にすぎず、決して主人ではない。だから実際の主人を無視するわけにはいかなかった。それゆえアンバンの力など、大したものではなかった |
19世紀半ば、ラサに滞在した2人のラザリスト会伝道師、ユックとガベも、アンバンの立場について同じようなことを書いている。
| 譬えるなら、チベット政府はローマ教皇で、中国人大使はローマ駐在のオーストリア大使だ |
ところで、ここに「中国人大使」と書かれているのはよくある間違いだ。清の政府はアンバンに中国人を任命したりせず、満人かモンゴル人を選んでいたのである。というのも、アンバンの任命はチュ・ユン関係の延長線上にあった行為であり、中国はそもそもチュ・ユン関係に関与していなかったからである。
1908年、チベットは清からかつてない侵攻を受け、両国に大きな分岐点が訪れた。それまでの派兵は、ダライ・ラマもしくはチベット政府を助けるものであり、チベットの要請によるものだった。ところが皇帝の今回の行動は、武力によってチベットに主権を確立し、当時チベットに高まりつつあったイギリスの影響力を駆逐するのを狙いとしていた。ダライ・ラマ13世は隣国インドに逃れたが、清のチベット占領は長くは続かなかった。
1910年、清がダライ・ラマの廃位を図ると、ダライ・ラマはチュ・ユン関係の終結を宣言した。保護者である皇帝が導師ダライ・ラマを攻めたことで、両者の関係は土台からひび割れてしまった。
侵略に対する抵抗運動は、1912年の清朝滅亡を受けて成就し、チベットは占領軍を降伏させた。同年夏、チベットと清はネパールの調停によって「3ヵ条協約」を結び、停戦と清軍の完全撤退を確認した。ラサにもどったダライ・ラマ13世は、1913年2月14日、チベットの独立を宣言した。